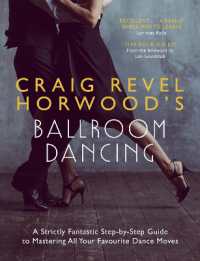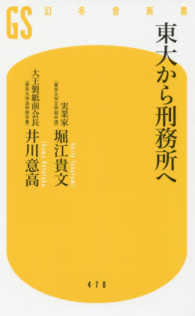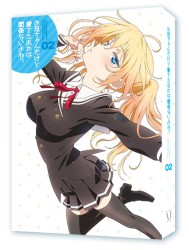出版社内容情報
人間にとって建築とはなにか? ふたつのオリンピックをつなぐ、圧巻の半自伝的文明論、登場!
内容説明
1964年、横浜・大倉山の“ボロい家”に育ち、田園調布に通いながら丹下健三に目を剥き、建築家を志す。無事にその道を進みニューヨークへ。帰国後のバブル崩壊で大借金を背負い、10年間東京で干される間に地方各地で培ったのは、工業化社会の後に来るべき「緑」と共生する次の建築だった。そして2020年、集大成とも言える国立競技場で五輪が開催される―自分史を軸に人間と建築の関係を巨視的に捉えた圧巻の一冊。
目次
第1章 1964―東京オリンピック(工業化社会は建築の時代;建築か、革命か ほか)
第2章 1970―大阪万博(1964という祭りの後;大阪万博での落胆 ほか)
第3章 1985―プラザ合意(武士よさらば;建築家も武士化 ほか)
第4章 2020―東京オリンピック(産業資本主義と金融資本主義;新国立競技場第一回コンペ ほか)
著者等紹介
隈研吾[クマケンゴ]
1954(昭和29)年、神奈川県生まれ。79年東京大学大学院建築学科修了。コロンビア大学客員研究員、慶應義塾大学教授を経て、2009年より東京大学教授。1990年に隈研吾建築都市設計事務所を設立、以後二十か国以上で建築を設計してきた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
32
隈氏と同い年だった。門外漢だった現代建築の歴史と自分の過ごしてきたあれやこれやが懐かしく蘇えらせてもらえる良書。代々木体育館、檮原(ゆすはら)町、登米能舞台、馬頭・広重美術館、長岡市役所、新国立競技場は本書を携えて訪ねたいところにリスト・アップ。2023/09/01
ばんだねいっぺい
31
面白い。建築を通じた日本社会の批評になっている。中でも、過去の功績を重視する温情主義のサムライ社会という見方やアフリカを調査するとき、数学を用いたあたりに感銘を受けた。2022/07/09
おいしゃん
21
新国立競技場を設計するまでを、生い立ちから振り返って書かれているので、隈さんのバックボーンや人間性が伝わってくる良作。特に隈さんの建築人生に大きな影響を与えた檮原村には、ぜひ行ってみたくなった。2021/09/30
さきん
21
隅研吾氏の建築はやはり小さくごちゃごちゃしている方が気を張ってなくて好き。大きい建築になると日本の森林資源がどうとか気張った感じになって背負うものが大きく、見ていて大変そう。建築の歴史は逆張りに逆張りで今は人類の力を誇示する建築よりも、自然とまじりあっていく建築が流行っているというおおざっぱな印象を受ける。2020/09/12
nomak
12
村上春樹ライブラリーが開館すると聞きつけたとき、隈研吾の設計ではあるまいなと嫌な予感がしたが、案の定だった。木材をぶっ刺してサステナブルとかプレスリリースすればオシャレで最先端と考える浅はかな人たちが目に浮かぶ。隈研吾の建築哲学が書かれているが、それはご立派。しかし、その持続可能うんちゃらが、便利な錦の御旗になっていやしないか。環境への綺麗事がデザインに必要なのは企業だ。田舎のイオンみたいなダサい新国立競技場の言い訳にはならない。なによりも、子供や若者の夢を高揚させる建築であることが大切だったとおもう。2021/03/11
-

- DVD
- シン・ジョーズ