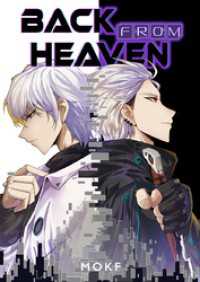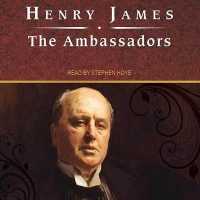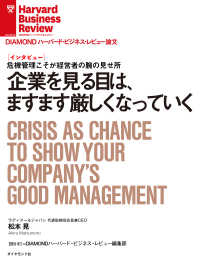出版社内容情報
「人材養成哲学」が勝敗を分けた――。日米英12人の戦歴簿。参戦各国の指揮官や参謀たちは、いかなるエリート教育を受けたのか。どの国も腐心したリーダーシップ醸成の方策とは何なのか――。「指揮統帥文化」という新たな視座から、日米英12人の個性豊かな人物像と戦歴を再検証。組織と個人のせめぎ合いの果てに現れる勝利と敗北の定理を探り、従来の軍人論に革新を迫る野心的列伝。
内容説明
「コマンド・カルチャー」から解き明かす「勝敗の定理」とは。参戦各国の指揮官や参謀たちは、いかなるエリート教育を受けたのか。各国が腐心したリーダーシップ醸成の方策とは何なのか―。「指揮統帥文化」という新たな視座から、日米英12人の人物像と戦歴を再検証。組織と個人のせめぎ合いの果てに現れる、勝利と敗北の定理を探った野心的列伝。
目次
第1章 「戦争になって、不充分な兵力で相当厄介な仕事にかかることになるか」アーサー・E・パーシヴァル名誉中将(イギリス陸軍)
第2章 「パーフェクトゲーム」三川軍一中将(日本海軍)
第3章 「これだから、海戦はやめられないのさ」神重徳少将(日本海軍)
第4章 「日本兵はもはや超人とは思われなかった」アリグザンダー・A・ヴァンデグリフト大将(アメリカ合衆国海兵隊)
第5章 「細菌戦の研鑽は国の護りと確信し」北條圓了軍医大佐(日本陸軍)
第6章 「空中戦で撃墜を確認した敵一機につき、五百ドルのボーナスが支払われた」クレア・L・シェンノート名誉中将(アメリカ合衆国空軍)
第7章 「諸君は本校在学中そんな本は一切読むな」小沢治三郎中将(日本海軍)
第8章 「猛烈に叩け、迅速に叩け、頻繁に叩け」ウィリアム・ハルゼー・ジュニア元帥(アメリカ合衆国海軍)
第9章 「これが実現は内外の情勢に鑑み、現当局者にては見込つかず」酒井鎬次中将(日本陸軍)
第10章 「おい、あの将校に風呂を沸かしてやれ」山下奉文大将(日本陸軍)
第11章 「殴れるものなら殴ってみろ」オード・C・ウィンゲート少将(イギリス陸軍)
第12章 「爆撃機だ、爆撃機を措いてほかにはない」カーティス・E・ルメイ大将(アメリカ合衆国空軍)
終章 昭和陸海軍のコマンド・カルチャー―一試論として
著者等紹介
大木毅[オオキタケシ]
1961年東京生まれ。立教大学大学院博士後期課程単位取得退学。DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生としてボン大学に留学。千葉大学他講師、防衛省防衛研究所講師、陸上自衛隊幹部学校講師等を経て著述業に。雑誌「歴史と人物」の編集に携わり、旧帝国軍人を多数取材。『独ソ戦』(岩波新書)で「新書大賞2020」大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
MUNEKAZ
ジュンジュン
CTC
gauche