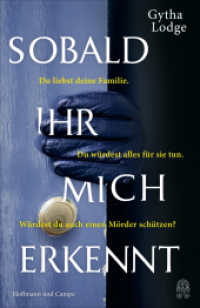出版社内容情報
「軍部にペンを折られた」は?だった。「報道報国」を掲げ、権力と一体化して部数拡大と特権獲得を図った新聞社の「不都合な真実」。
内容説明
第二次大戦後、新聞社はこぞって言い始めた。「軍部の弾圧で筆を曲げざるを得なかった」と―。しかし、それは真実か?新聞の団体は、当局に迎合するだけの記者クラブを作り、政府の統制組織に人を送り込んで、自由な報道を自ら制限した。「報道報国」の名の下、「思想戦戦士」を自称しつつ、利益を追求したメディアの空白の歴史を検証する。
目次
一万三四二八紙の新聞
変貌する報道メディア
国策通信社の誕生
実験場としての満州
新聞参戦
映画の統合
内閣情報局に埋め込まれた思惑
自主統制の対価
新聞新体制の副産物
統制の深化
一県一紙の完成
悪化する戦局の中で
巣鴨プリズン
著者等紹介
里見脩[サトミシュウ]
1948年、福島県生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得満期退学。博士(社会情報学)。時事通信社記者、四天王寺大学教授、大妻女子大学教授などを経て、現在は大妻女子大学人間生活文化研究所特別研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
128
WW2に於ける、軍部・政府との関係を政府系通信社「同盟通信社」社長にして斯界の大立者古野辰之助を中心に追った新聞業界史。人事闘争モノの企業小説とか財界小説なんかが好きな人にはお勧め。軍部の「弾圧」とやらを掻い潜り、戦争で焼け太った新聞業界を克明に描いて余す所なし。新聞は昨日今日腐ったわけではなく、戦時中には既に腐臭を放つような存在であったことが理解できる。ただ、その腐りようが発信される手段が少なかっただけのことである。人の営みの下らなさに頭を抱えたくなったことである事だよ。2023/04/13
trazom
103
戦時下、メディアは、軍部による「言論統制」の被害者ではなく、むしろ、それに便乗し自らのビジネスの拡大に邁進した存在だった。朝毎読の販売競争、全国紙と地方紙との競合、通信社と新聞との関係などの企業意識が優先され、戦争が儲けの手段となる。その象徴的人物として、古野伊之助、正力松太郎、緒方竹虎らが権力闘争に明け暮れる姿が描かれている。戦時統制で生まれた特権(一県一紙、記者クラブなど)が、権力とメディアの癒着構造として今に続いていることが問題だ。敗戦と同時に報道メディア全てを廃社にしたドイツとの違いがここにある。2021/11/14
パトラッシュ
93
戦時中は軍の発表以外は書くことを許されず、多数あった地方紙は政府の強制で1県1紙に統合されたなど新聞を戦争の被害者とする従来の史観を転覆させられる。積極的に戦争を支持する新聞が「報道報国」の名で販路を拡張し、記者クラブ設立などで政府に迎合し自由を放棄した実態が生々しい。資本の小さな中小紙はむしろ統合に活路を見出し、当時得た特権を今も握り続けている。紙の新聞は毎年10万部以上減り続けており、そう遠くない将来に消滅するだろう。古野や正力や緒方が21世紀の業界を見れば、自分たちの活動の虚しさに愕然とするのでは。2021/12/16
まると
24
戦争という国策推進のため、軍部への協力を深めていった新聞の歴史をたどっている。大まかに言うと▽日中戦争の速報で部数を伸ばした全国紙が地方紙に攻勢▽地方紙を束ねる同盟の古野が対抗、軍部と結託して自主統制組織により報国報道を主導▽各社生き残りのため軍部の統制にのみ込まれたーーという流れ。軍部が主導した一県一紙政策で経営が安定したのに各社はその歴史を顧みず、戦時下の記者と同様、今の記者もサラリーマン意識で発表を鵜呑みにして記事を書いていないかとの指摘は傾聴すべきだろう。この内容でこのタイトルはちょっと違うかな。2024/06/23
史縁
7
戦時中の言論統制ではメディアはとかく被害者面しがちだが、新聞社はむしろ積極的に統制に関与した。記者クラブ経由で政府の公式発表を伝えるだけの存在になったり、一県一紙で経営基盤を固めたりなど戦時中の言論統制の仕組みが現在も引き継がれていることが興味深かった。 現在は、既存メディアへの信頼性が低下、インターネットではフェイクニュースが散乱し、またメディアでない一般人も自由に発信することが可能になっている。メディアが公権力におもねない姿勢はもちろん、利用者も発信することへの責任が問われている。2025/04/23