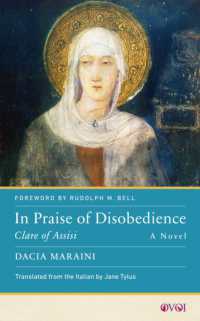出版社内容情報
本当のSDGsは足元にあった!列島改造から半世紀、経済成長に疲れた僕らが安心して暮らし続けるための「日本の潜在力」の引出し方
内容説明
日本列島を根本から理解すると見えてくる、その凄まじいまでのポテンシャル。驚異の近代化や数々の復興の原動力となった「国土」と「地方」は、いま再び、未来に不安を抱きつつある私たちを救ってくれるのか。自然、歴史、コミュニティ、テクノロジーを総動員して構築する、全く新しいSDGs、イノベーションの思想。
目次
第1章 この国の行く末
第2章 求められる安心の基盤
第3章 山水郷の力
第4章 動員の果てに
第5章 山水郷を目指す若者達
第6章 そして、はじまりの場所へ
著者等紹介
井上岳一[イノウエタケカズ]
(株)日本総合研究所創発戦略センターシニアスペシャリスト。1994年東京大学農学部卒業。Yale大学修士(経済学)。林野庁、Cassina IXCを経て、2003年に日本総合研究所に入社。森のように多様で持続可能な社会システムの実現をめざし、官民双方の水先案内人としてインキュベーション活動に従事。現在の注力テーマは「ローカルDXによる公共のリノベーション」。南相馬市復興アドバイザー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
38
題名は田中角栄の日本列島改造論へのアンチテーゼ。土建国家の限界を踏まえてこれからの日本は「山水郷」を活かしていくべきだと説く。現物給付より現金給付を重視したのが土建国家だった。その結果「お金があればなんとかなるけど、お金がないと何ともならない社会」になったとの指摘は的を射ている。映画「男はつらいよ」の葛飾柴又のようなコミュニティ社会の喪失とも言える。最近は、こんな社会構造に限界を感じた若者達が山水郷に集まりつつある事に、著者は希望を見出す。個を尊重するムラ社会を作れるかがカギになるように思う。2020/12/01
Sakie
23
未来の日本人の回帰地点はどこにあるのだろう。日本人の未来という漠としたものを考えるのも飽きてきたが、確かなのは、減る一方の日本人が中央/地方の都市だけに集まって暮らすことが現実的でないことだ。国土やインフラを維持するためには辺境で山林の手入れをする人が必要で、辺境に生活する人がいれば交通網と通信網を含めたある程度のインフラは整備し続ける必要がある。金は無い。「ぽつんと一軒家」ではないが、傷みが進まないよう、ある程度自分たちで維持する努力は必要だろう。社会は自分の事だけをすればよいのではなくなっていくのだ。2023/07/29
99trough99
22
給料が上がらず、未来に希望を持てない今、さらに人口減少が拍車をかけて、日本の未来は暗いという見方をよく目にする。本書では、そうした閉塞感を田舎すなわち山水郷回帰によりブレークスルーしようという提案に満ちた提言書である。日本の歴史を弥生時代から紐解き、土建型社会すなわちお金が全ての時代になったのはわずかここ150年ほどであることを示し、その上で(著者は具体策を示さなかったとあとがきで述べてはいるが)過去と未来を合わせた発展形を山水郷に導入することで明るい未来が見えると訴える。 大変な説得力に満ち溢れた書。2022/10/30
おせきはん
20
国内の地方で生き生きと生活する人々の事例を踏まえ、自然の恵みと人々のつながりが残る山水郷を足場とする生き方を提唱しています。山水郷で生活を完結させる、あるいは山水郷に住み地方都市で働く生き方は、少なくとも、お金やモノや出世をそれほど重視しない人々にとっては十分に検討に値する選択肢だと思いました。2020/02/21
まゆまゆ
16
列島改造ではなく、列島回復へ。かつての成長モデルだった土建国家の推進と減税による政策は終わり、代わりに経済格差による国民の分断が発生。他者への不寛容さが目立つようになり、都会での生活を諦めて田舎らしさを求めて移住する人達も増えている今こそ、先を見据えて自然と向き合うべきである。物より心の豊かさを求める時代になり、自然からの恵みに感謝しともに生きることが必要ではないか。自然を維持するためには共存が必要であり、そこは人々を引き受ける契機に満ちている。2020/01/16