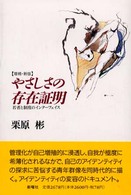出版社内容情報
芥川、漱石、鴎外、小林秀雄、深沢七郎、三島由紀夫ー。近代日本文学の名作を、解剖学者ならではの「身体」という視点で読み解いた画期的論考を選書化。
内容説明
三島由紀夫の割腹とホムンクルスの関係とは。芥川龍之介はなぜ中世に惹かれたのか。深沢七郎の真骨頂は一体なにか。日本文学の「転換期」とはいつなのか。他に夏目漱石、森鴎外、小林秀雄、大岡昇平、石原慎太郎らの近現代文学の名作を、解剖学者ならではの「身体」という視点で読み直し、新たな歴史観を呈示する一冊。加藤典洋氏との対談を追加して選書化。
目次
身体の文学史
芥川とその時代
心理主義
文学と倫理
身体と実在
自然と文学
深沢/七郎ときだみのる
戦場の身体
太陽と鐵
表現としての身体
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ]
1937年、鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年、東京大学医学部教授を退官し、同大学名誉教授に。89年、『からだの見方』でサントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-