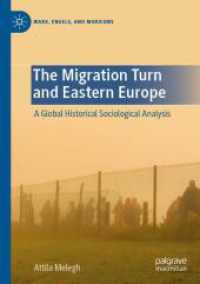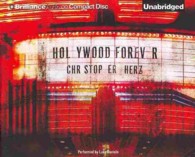内容説明
人生五十年の時代、戦国武将たちには謡曲『敦盛』の一節の如く「この世は夢幻の間」であり、生きている短い間よりも死後の長い時間を強く意識していた。武士の臨終は人生の終わりではなく、そこから始まる長い来世へのとば口。死に際はその門出を飾る大切な場だったのだ…彼らの信念、死にざまと関わりの深い疾病について、現代医学と照応しつつ実態を探る。
目次
第1章 三英傑 信長・秀吉・家康の死にざまと死生観
第2章 病苦にあえいだ英雄たち
第3章 この世に未練を残した武将たち
第4章 下克上の梟雄たち
第5章 切腹して果てた武将たちの執念
第6章 老衰死した武将たちの高齢期
第7章 夫におとらず厳しい道、戦国女性の覚悟
第8章 戦国武将と女性たちのカルテ
著者等紹介
篠田達明[シノダタツアキ]
1937年愛知県生まれ。医師にして作家。名古屋大学医学部卒業。心身障害児医療を専門とする。愛知県心身障害者コロニー・こばと学園園長を務め、現在、同学園の名誉総長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
れみ
58
戦国時代の武将や女性たちがかかった病、生き死にについての考え方などを残された文書などから考察。戦国武将のように死を身近に感じる境遇ではないから死生観について考えることは難しい気はするけど、死に様を考えることは自分がどう生きたいかとか何が生きがいなのかということを見つめ直すことだと考えれば、なんとなく答えというか方向が見えてきそうな気もする。2015/03/21
smatsu
5
著者は医師・作家で、天下人となった三人を筆頭に戦国時代の有名な武将の死に様と、医者の観点からの死因の見立て、そしてその武将が死を目前にして何を考え、どんな思いで死を迎えたであろうかを推察する。武将だけでなく周辺の女性なども考察対象になっています。よく調べてあり、淡々とした筆致に味わいがある本だと思います。今回はとりあえずざっと通読したのですが、自分がもう少し歳を取って死が現実感を持って近づいてきたときにまた改めて読み直してみたい本ですね…たいへん面白い本でした。ありがとうございました。2022/07/31
ミルチ
4
著者が元医師という経験から戦国武将の死因を現代医学の立場から推測しているのが新鮮で興味深かった。また信長ADHD説や秀吉6本指説もヘーッ!って感じで面白い。大半はこんな感じで死生観?って感じだったが、最後に著者の死生観孝によって締め括られるので満足した。友人のオススメ本、ナイスでした!2015/09/06
maito/まいと
3
戦国時代の著名人たちの生涯を、医学的観点から紐解いた1冊。非常に素人にも分かるような書き方がされていて、非常に好感が持てた。後半の死生観と現代への批判・提言については意見の分かれるところだろうけど、この薄情な今の社会にて生き続けるための、一つの目線としては忘れてはいけない要素だとは思った。2010/11/26
ほしけも
2
戦国武将の死因を文献から医学的に推理してるところが面白い。 武将たちは寿命が短いからこそ現世のことよりも後の世での評判とか、 死に様を第一に考えて、みっともない生き方をするくらいだったら 華々しく散りたいっていう感覚。人生を物語のように思ってたのかな。 北欧の戦士も藁の上で死ぬことを恥としたというから 生きるか死ぬかという苛烈な時代の人間の死生観というのは そういうものなのかね。 2012/11/07
-
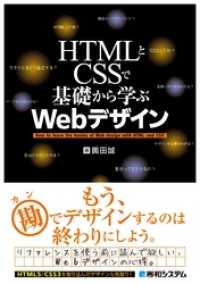
- 電子書籍
- HTMLとCSSで基礎から学ぶWebデ…