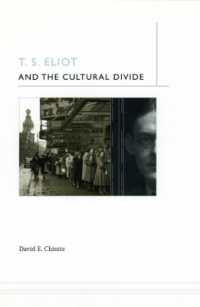内容説明
幾多の激戦の末にスペイン軍を撃破、植民地の軛から中南米諸国を解き放ち、ついに独立へと導いた輝ける将軍シモン・ボリーバル。ラテンアメリカ統合の理想実現に燃えてひた走った英雄は、なぜ失意の迷宮に踏み入らねばならなかったのか?“解放者”と称えられた男。その最後の七ヵ月、コロンビアの大河を暗然と下りゆく死への旅路は。―栄光という闇の深さを巨細に描き切る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
172
南米史に燦然とその名を残す実在の「解放者」シモン・ボリバルを描く。ただ、マルケスは盛時をではなく、マグダレーナ河を下る将軍最後の旅を語る。1930年5月8日から12月17日の死までだ。ここでのマルケスの語りは、いわゆるマジック・リアリズムと呼ばれるそれではなく、むしろジャーナリスティックなものにも見える。しかし、ここに描かれる時間や空間は、時には交錯しつつ、また時には過ぎ去った夢幻のごとき様相を呈したりもする。イスパノ・アメリカ世界の統一を庶幾したボリバル。しかし、そこは終わってみれば「迷宮」だった。2014/07/12
どんぐり
73
19世紀ラテンアメリカの独立運動の指導者シモン・ボリバル最期の日々を描いたガルシア=マルケスの歴史小説。メキシコからホーン岬にいたる大陸統一という黄金の夢を抱き、マグダレーナ河を下っていく将軍の道行き。“ヌエバ・グラナダ共和国”“大コロンビア”の歴史をひもときながらこの小説を読むと、「われわれはスペイン人であることをやめ、その後、毎日のようにころころ名称と政府の変わる国々を渡り歩いてきた。おかげで、今現在自分がどこにいるのか分からないというのが実情なんだ」という将軍と共に迷宮の中にはまり込む。2020/02/01
ころこ
48
革命とは現実政治の問題と思想的な実現とのに側面がある。シモン・ボリバルが世界的に注目されないのは、現在のベネゼエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビアがことごとく経済的にも社会的にも問題の多い国々であること。また思想的にもリベレイターであったことが(フランス革命の後にフランスで影響を受けている)、新しい価値を創造するに至らなかったことに起因するのではないか。フランス革命に倣ったことがアメリカ革命との200年後の差を生んでいるのか、それともウェーバーが考えるようにプロテスタントとカトリックとのエートス2025/04/17
chanvesa
39
現代の感覚からしたら47歳にしては病気とは言え、老成した人間を描写しているように感じる。しかし老いを感じさせるのは、戦争、政治、権力闘争をくぐり抜け君臨してきたはずの人間が、「迷宮」と表現せざるを得なかった人生にかなりくたびれた故なのだと思う。「人と争って千回勝つよりも、気持よく一回和解するほうがずっといい」(256頁)なんて軍人の言葉とは思えない。独裁者でも英雄でもなく、死と直面する孤独な人間の記録であり、召使のホセ・パラシオスや永遠の恋人の様なマヌエラ・サエンスとの絶妙な距離加減も孤独を深くしている。2016/06/25
ホームズ
29
なんだろう凄く良い雰囲気だった。暗く陰鬱な感じなのになんだか読んでいるととても心地がいいというかなんというか。どんどん読んでしまった。南米の英雄シモン・ボリバルの失意の晩年と過去の栄光の描き方が良かったな~。「私には自分を犠牲にしてもいい祖国はもはや存在しない」という言葉が印象に残った。ちょっといい本を読んだので次に読む本がかなり難しい気がする。2013/02/12