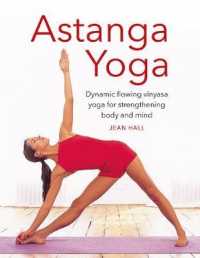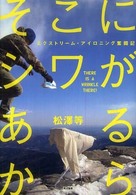出版社内容情報
日本の資本主義を創ってきたリーダー達は何を考え、何を成し遂げたのか。『バブル』の著者が最前線で目撃した彼らの光と影を描く。東芝、トヨタ、三菱、セブン&アイ。会社を「滅ぼす」のは誰か。なぜ今、日本を代表する企業で不祥事や内紛が相次ぐのか。戦前のカネボウから現在のソフトバンクまで、日本をリードしてきた企業の栄枯盛衰と、その企業の命運を決した経営者達の決断と葛藤を描き、日本企業と日本の資本主義のあるべき姿を問う。話題作『バブル』の著者が最前線で目撃してきた、経営トップ達の壮絶なるドラマ。
永野 健二[ナガノ ケンジ]
著・文・その他
内容説明
三菱、トヨタ、セブン&アイ、東芝…会社を「滅ぼす」のは誰か。企業の命運を決めたリーダー達の葛藤と決断。
目次
第1章 戦後日本経済のリーダーたち(武藤山治とカネボウの「滅びの遺伝子」;二度引退した“財界鞍馬天狗”中山素平 ほか)
第2章 高度消費社会の革命児たち(中内〓(いさお)―流通革命と『わが安売り哲学』
伊藤雅俊と鈴木敏文、今生の別れ ほか)
第3章 グローバル時代の変革者たち(ジョブズになれなかった男、出井伸之;“最後の財界総理”奥田碩の栄光と挫折 ほか)
第4章 新しい時代の挑戦者たち(柳井正の永久革命;豊田章男が背負う「トヨタの未来」 ほか)
著者等紹介
永野健二[ナガノケンジ]
1949年生まれ。京都大学経済学部卒業後、日本経済新聞社入社。証券部の記者、兜クラブキャップ、編集委員として、バブル経済やバブル期の様々な経済事件を取材する。その後、日経ビジネス編集長、産業部長、日経MJ編集長として会社と経営者の取材を続け、名古屋支社代表、大阪本社代表、BSジャパン社長などを歴任した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
信兵衛
西
すうさん
templecity
trazom
-

- 電子書籍
- 死の瞬間 人はなぜ好奇心を抱くのか 朝…
-
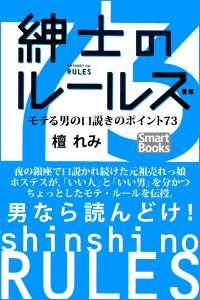
- 電子書籍
- 紳士のルールズ モテる男の口説きのポイ…