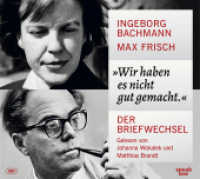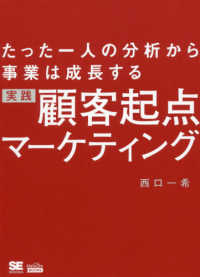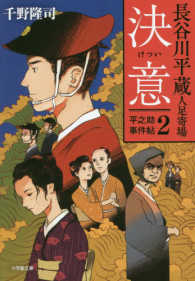出版社内容情報
余命少ない子供が治療から離れ、家族と生涯忘れえぬ思い出をつくれる場を。民間小児ホスピス誕生から日々の奮闘まで、感動の記録。
内容説明
余命少ない子供たちが辛い治療から離れ、やりたいことをのびのびとやり、家族と生涯忘れえぬ思い出をつくる。そんな、短くとも深く生きるための場所があったら―。医師や親たち関係者の希望をたずさえ、「こどもホスピス」が大阪、鶴見に誕生した。実現に向けて立ち上がった人たちのこれまで、そしてこれから。貧困やネグレクトなど子供の問題を描いてきた著者が、あらたに問いかける一冊。
目次
第1章 小児科病棟の暗黒時代
第2章 英国のヘレンハウス
第3章 大阪市中央公会堂
第4章 小児病棟
第5章 プロジェクト始動
第6章 TSURUMIこどもホスピス
第7章 短い人生を飾る
第8章 友のいる家
著者等紹介
石井光太[イシイコウタ]
1977(昭和52)年、東京生れ。国内外の文化、歴史、医療などをテーマに取材、執筆活動を行っている。ノンフィクション多数。また、小説や児童書も手掛けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





TERU’S本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゃちゃ
121
子どもが子どもらしく生きるために“友として寄り添う”場、それがこのホスピスのスタンスだ。ホスピスというと死を看取る場という印象が強いが小児医療の場合は少し意味が異なる。辛い治療現場を離れて笑顔で過ごすための場なのだ。2016年大阪鶴見に設立された日本初の「こどもホスピス」は、多くの人たちの強い願いと祈りと奮闘によって誕生した。いたずらに苦しい延命措置を図るより、「LIVE DEEP」。短くても充実した最期を過ごすことが、逝く者にも遺る者にも、いかに幸せをもたらすかを伝えてくれる素晴らしいノンフィクション。2021/04/29
ぶち
107
読友さんのレビューを拝見して知った本です。ホスピスと聞くと末期患者が息を引き取るまでの"看取り"ケアが心に浮かびます。"こどもホスピス"は違います。子供たちが辛い治療の場から一時離れ、家族や友人と笑い合って生涯の思い出をつくる"家"としての空間なんですね。成人のホスピスとは異なる考え方で運営されるこどもホスピスが病院の論理や規則から離れた場所に必要なのだということが、この本に登場してきた子供たちの闘病生活を垣間見させていただいて、しっかりと理解できました。読んでよかったと思えるドキュメンタリーでした。2021/10/23
モルク
105
ここで言うホスピスは、看取りの場と言うより患者と家族に休息を与える場である。厳しい闘病生活を送っている病児たち。彼らの望みは家族に囲まれごく普通の子供として勉強したり遊んだりすることである。しかし病院や親の都合で入院生活を伸ばし、辛い治療を施すのが現実だった。それよりも、残りの人生を精一杯過ごし楽しい思い出作りをするのが双方の幸せに繋がるとの理念のもと立ち上げられたプロジェクト。あくまで主役はこどもたち。彼らの笑顔のために…と、関わった方々の苦労は計り知れない。読むときはハンカチ、ティッシュと共に。2021/02/17
trazom
97
大阪市鶴見緑地にある民間の小児ホスピス「TSURUMIこどもホスピス」の物語。施設の開業に至るまでの、医師、看護師、保育士、保護者たちの試行錯誤の物語が、志半ばにして天に召された多くの子供たちのエピソードとともに胸に迫ってくる。医学を駆使した延命作業に疑問を持ち、こどもたちと家族の日常を満ち足りたものにするためにどうしたらいいかを模索する人たちの誠実さが、この施設の原点である「友として寄り添う」という言葉に込められている。背景に余りにも多くの悲しい物語を背負っているからこそ、善意が透き通って心に沁みる。2021/01/29
itica
83
「TSURUMI こどもホスピス」は難病の子どもや家族に居場所を提供し、支援して行くことを目的として作られた。医師も家族も少しでも長く生きていて欲しいと願う。しかし辛い延命治療の末に逝った子どもは幸せだったのだろうか。長い闘病後、家に戻ってどうやって一般社会に馴染むのか。そんな疑問の中、生まれたこどもホスピス。子どもに笑顔が戻ったことや生きがいを見つけたこと、家族が救われたことに、こどもホスピスの存在の意義を強く感じた。 2023/05/28