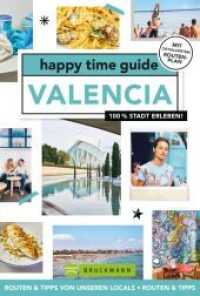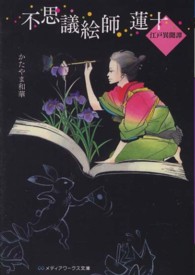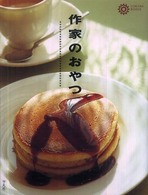内容説明
木はしっかりした意志があるものであって、筋の通った注文しか受けつけない―。山に囲まれた裏木曾の小さな村で、日常生活に用いられる家具や道具を一つ一つ手仕事で製作し続けて四十余年。素材としての木に真剣に取り組み、新しい形を与えることで、その魂を蘇らせてきた名匠が、さまざまな木、工具、製作現場、師と仰ぐ人物との出会いを綴った、木の香りが立ち昇るエッセイ集。
目次
北窓から―まえがきにかえて
私にとっての木
道具のこと
木と組む
裏木曾に暮して
師
著者等紹介
早川謙之輔[ハヤカワケンノスケ]
1938(昭和13)年、岐阜県付知生れ。県立中津高校卒業後、木工の世界に入る。’69年、付知に「杣工房」を設立し、家具、道具の製作に携わる。’74年から隔年ごとに「盆」「額縁」「座卓」とテーマを決めた個展を開く
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
25
御嶽山の南、木曽山脈の西に位置する町に学校でてから50年以上、家具づくりに携わってきた。椅子や机、小箱が多いが、美術館の天井にも挑戦したことがある。木の乾きによる縮みを見越して材を取る。著者のお気に入りはケヤキやヒノキの大径木から取れる太い一枚板。終戦直後までは木曽山脈からヒノキの大径木がたくさん取れた。図や写真が少ないのが残念。2021/11/11
itokake
11
木工職人のエッセイ。職人らしい実直な文章で専門用語も多い。一番面白かったのは、正倉院の柿厨子を「そこいらの木工がポンポンと作った実用品」と見破ったところ。私は正倉院にあるものは、全て匠の作品だと思っていた。見破った決め手は2つあり、①右扉についている定規縁が平行でも上下対称でもない②裏板下部についているシミと、扉の端喰に打たれた鉄くぎのさび跡。①は木を乾燥させるまえに制作したので、木が縮んだのを補修したから②はアク抜きしない木材でつくったから。実用品も年月が経つと宝物になるって、なんかいいな。2021/12/02
midorikawa-e
2
なんらかの分野にきちんと向き合ってきた人の語りが好きです。加えて、この方の場合、文章そのものも良いです。2014/10/06
ふう
1
木工のプロ、ということで、文章よりも作品を見たいと思った。静岡県立芹沢銈介美術館の天井張り。見てみたい。 週末、たんげ温泉美郷館で木の贅沢をしてきます。一本一本木の価値の出る挽き方をして、それから木の使い道を考えた、という贅沢な世界。日本の木の文化をもっともっと知りたい。2014/08/22
志村真幸
0
1993年に出た単行本の文庫化。新たに5篇が加えられている。 「杣工房」を主宰する木工家として知られた著者のエッセイ30篇を集めたもの。 「百枚の盆」「檜」「椅子・チェスト」「桜」「鋸」「鉋」「材を乾かす」「裏木曾に暮らして」「黒田辰秋先生」といった文章が並んでいる。 いずれも「こだわり」を感じさせる内容である。頑固で偏屈で妥協せず、ひたすらに木や道具や自分の技術を見つめ続ける。しかし、それをちゃんとわかるように説明してくれているから、おもしろい。 2018/10/04