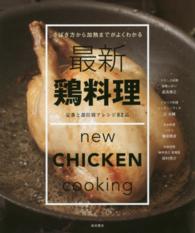出版社内容情報
本郷の下宿屋から青森の旧家へと流されてゆく晴子。ここに昭和がある。あなたが体験すべき物語がある。『冷血』へ繋がる圧倒的長篇。
両親を失った晴子は福澤家で奉公を始める。三男二女を擁する富と権力の家――その血脈は濁っていた。やがて運命に導かれるように、末弟たる異端児淳三と結婚する。一方、母の告白により出生の秘密を知った彰之は、苛酷な漁に従事しながら、自らを東京の最高学府から凍てつく北の海にまで運んだ過去を反芻する。旅の終りに母子が観た風景とは。小説の醍醐味、その全てがここにある。
内容説明
両親を失った晴子は福澤家で奉公を始める。三男二女を擁する富と権力の家―その血脈は濁っていた。やがて運命に導かれるように、末弟たる異端児淳三と結婚する。一方、母の告白により出生の秘密を知った彰之は、苛酷な漁に従事しながら、自らを東京の最高学府から凍てつく北の海にまで運んだ過去を反芻する。旅の終りに母子が観た風景とは。小説の醍醐味、その全てがここにある。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
391
難渋しつつも読了。読後はなんとも寂寥感に満ちた感覚に捉えられることになる。晴子と彰之のそれぞれが抱える孤独は、荒涼たる荒野を吹きすさぶ寒風のようだ。晴子が書き続ける手紙は、彰之に向けたものでありつつも、実態は晴子自身の自己省察の語りであっただろう。作家の側からすれば、その時代を「書く」ことによって生き直す(それ自体が虚構なのだが)営為に他ならなかった。一方、彰之の思いが語られることはない。北の海にあって、その寡黙が語る語るものは何だったのだろうか。2020/05/19
KAZOO
119
高村さんが本当に書きたかったことなのでしょう。いままでの作品を読んできた方には肩透かしかもしれません。母親が息子にあてた手紙と最高学府を出たものの漁労員になっている息子の生き方がフラッシュバックのように交互に語られますが大きな事件らしい事件はありません。母親がその両親の生きざまを語り、あるいは自分の生涯を語り、また息子がそれまでに生きてきた時代を語ることにより大正昭和の時代を俯瞰しているような感じがしました。私はこの息子の年と近いので非常に興味を持って読むことができました。福澤サーガですね。2023/01/03
もりくに
64
私は「読書」は勿論好きだが、本を「集める」ことはもっと好きなようだ。だから、「あれも読める」「これも読める」と本棚を眺めて、幸せな気分に浸っていたが、70代後半と齢を重ねて、今では「あれも読んでない」「これも読んでない」とジリジリしている。この青森の福澤家三部作は、「あれも読みたい」に確実に入っていたので、まだ三合目だが「高峰」を歩き出した喜びが少しある。インタビューで高村さんは、「阪神大震災を経験して、(自分の)何かが変わった」と述べていた。そしてこのシリーズは、その2年後から書き出されている。→ 2025/03/07
もりくに
62
信頼できる読友さんのエールに応えて、拾い読みして「巨象」の足をもう一掻き。高村さんは1995年、人生の突然の分断という危機に直面した阪神淡路大震災を経験して、歴史、それも記録に残らない普通の人々の生活を、書こうとしたのではと思う。福澤(野口)晴子の息子(彰之)への手紙という形で。彰之は母からの手紙で、普通はあまり知らない母になる前の「晴子」という女性の人生も知り、激しく揺さぶられもしたが、彼も船上で手紙を何十回と読み、自分の半生を考える契機ともなった。晴子を軸とした、大正から昭和(敗戦から戦後)の物語。→2025/03/18
NAO
62
時代に翻弄される女性、東北地方という辺鄙な地に暮らす人びとの生活の暗さ、福澤家という何とも得体の知れない旧家の奥底に潜んでいるもの。晴子の手紙の饒舌すぎる語りに対し、彰之の段は、夢の中なのか、思い出にふけっているのか、現実のことなのかよく分からないような混沌とした意識の流れの描写が続く。最高学府を出ながら、陸からはるか離れた漁船の中、荒波にもまれ力仕事に身体を痛めつけて、それでも確固たる信念を持てないまま、日々鬱々と懊悩し続けるしかない彰之の姿の痛ましさこそが、福澤家が抱える闇であり、時代の闇なのだろう。2017/08/23
-
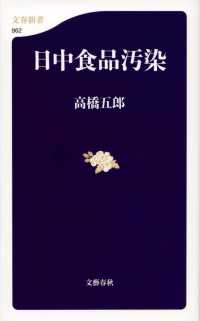
- 和書
- 日中食品汚染 文春新書
-

- 和書
- 疫学辞典 (第5版)