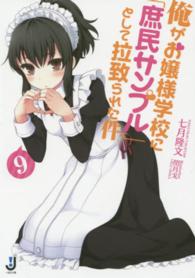出版社内容情報
直径わずか1.6ミリ。幻の卵を求め太平洋を大捜索! ウナギ絶滅の危機に挑み「世紀の発見」をなしとげた研究者の希有なる航海。
海で孵化して半年、その後姿をかえて川で十年、再び海へ産卵に戻る不思議な生態のウナギ。何千キロも大洋を回遊するウナギ最大の謎はその産卵場だった。海の塩分濃度、海底山脈の位置、月の満ち欠け。様々な仮説の検討の結果、浮かび上がってきたのは西マリアナ海嶺の南端部の海山域だった。広大な海で直径1.6ミリの卵を探しあてた世紀の大発見の軌跡。「世界で一番詳しい ウナギの話」改題。
内容説明
海で孵化して半年、その後姿をかえて川で十年、再び海へ産卵に戻る不思議な生態のウナギ。何千キロも大洋を回遊するウナギ最大の謎はその産卵場だった。海の塩分濃度、海底山脈の位置、月の満ち欠け。様々な仮説が検討され、浮かび上がったのは西マリアナ海嶺南端部の海山域だった。広大な海で直径1.6ミリの卵を探しあてた世紀の大発見の軌跡。
目次
第1章 なぜ、動物は旅に出るのか―ヒトも魚も「脱出」する
第2章 ウナギの進化論―深海魚がウナギになった?
第3章 二つのウナギ研究―大西洋と太平洋
第4章 海山に「怪しい雲」を追う―三つの仮説、検証の一四年
第5章 ハングリードッグ作戦―幸運の台風遭遇
第6章 ウナギ艦隊、出動ス!―世界初の天然卵採集、親ウナギ捕獲
第7章 なぜウナギ資源は減少したか―原因の究明と研究の進展
第8章 ウナギ研究最前線―研究はエンドレス
第9章 ウナギと日本人―保全のために今私たちができること
著者等紹介
塚本勝巳[ツカモトカツミ]
1948(昭和23)年岡山県生れ。農学博士。専門は海洋生命科学。’71年東京大学農学部水産学科を卒業、’74年東京大学大学院農学研究科博士課程を中退後、同年、東京大学海洋研究所の助手。’86年助教授、’94(平成6)年教授に就任。現在は日本大学生物資源科学部教授。独自の「海山仮説」「新月仮説」「塩分フロント仮説」に基づき、世界で初めて天然ウナギの卵をマリアナ諸島西方海域で採集することに成功。その研究功績から、2006年日本水産学会賞、’07年日本農学賞・読売農学賞、’12年日本学士院エジンバラ公賞、’13年海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)など多数の賞を受賞している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
UK
七月せら
bb
さきん
tsubomi
-

- 和書
- 学問で平和はつくれるか?