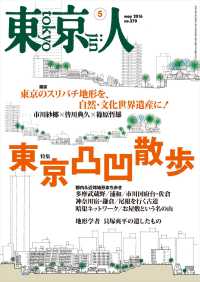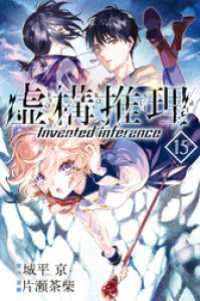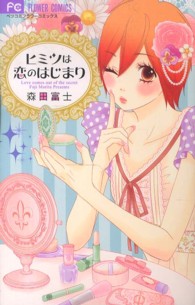内容説明
「一応ノーベル賞はもらっている」こんな学者が濶歩する伝統の学府ケンブリッジ。家族と共に始めた一年間の研究滞在は平穏無事…どころではない波瀾万丈の日々だった。通じない英語。まずい食事。変人めいた教授陣とレイシズムの思わぬ噴出。だが、身を投げ出してイギリスと格闘するうちに見えてきたのは、奥深く美しい文化と人間の姿だった。感動を呼ぶドラマティック・エッセイ。
目次
第1章 ケンブリッジ到着
第2章 ミルフォード通り17番地
第3章 研究開始
第4章 ケンブリッジの十月
第5章 オックスフォードとケンブリッジ
第6章 次男が学校でなぐられる
第7章 レイシズム
第8章 学校に乗り込む
第9章 家族
第10章 クイーンズ・カレッジと学生達
第11章 数学教室の紳士達
第12章 イギリスとイギリス人
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いちねんせい
40
アメリカでの生活を描いた前作が非常に面白く、こちらも手にとった。今回も複雑な愛国精神に共感すること多し。ただ個人的に途中から各章を終える際のドラマチックな?スタイルなどが食傷気味に。もう少し時間を置いて読めばよかったか。それでもやはり面白かったのだが!2019/08/05
おいしゃん
37
秀作!はじめはとっつきづらく、全く良い印象の持てないイギリス社会に、順応し溶け込んでゆく数学者一家を間近で見守っているかのような気分になり、ラストシーンは感動必至。2019/08/31
inami
28
◉読書 ★3.5 日本にいる時は、日本や日本人の悪口ばかり言っているのに、国外に出ると一切の批判を許せなくなるという藤原さん(数学者)、本書は1987年8月から、長期在外研究員としてケンブリッジ大学に赴むいた(家族も一緒)約1年間の生活ぶりを描いたもの。イギリス人の性格や国民性がみごとに伝わってくる。日本人とイギリス人とは、心底に無常感を抱いているという点で、本質的によく似ているという。南木さんの解説に「心理の探求の手段が数学でなく文学だったら、第一級の小説家になっていたはず」とある、おっしゃるとおりです2019/03/28
Kajitt22
28
ふた昔以上前のケンブリッジ留学の奮闘記だが、アカデミックなオックスブリッジは今もあまり変わらないのかなと想像しながら読んだ。自らの汗で築いた財産は見下されることが多く、遺産として継承した財産は肯定されうらやましがられるとは、まさに驚きだ。数年前仲良くなった、イギリス、ブリストル生まれの青年はユーモアのある気のいい男だったが、家族の写真などからたぶんロウワークラスの出だったかもしれない。ヨーロッパには厳然とクラスが存在しているのだ。再読2015/08/07
バトルランナ-
19
こんなジョークをどこかで読んだ覚えがある。 「無人島に男2人と女1人を漂着した。 男たちがイタリア人なら殺し合いになる。 フランス人なら1人夫、1人は愛人となってうまくやる。 イギリス人なら、紹介されるまで口をきかないから何も起こらない。 そして日本人なら東京本社へファックスを送りどうすべきか問い合わせる。」 そのほかの文章もリズムがあって美しい。 4.4点。2020/04/07