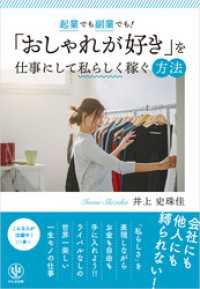内容説明
考える―その一言で表されてしまう行為は、これほどまでに多様なものなのか。ある者にとっては「考える」=「見ること」であり、ある者にとって思考は「歩くこと」と密接に結びついていた。小林秀雄、福田恆存、武田百合子、幸田文、植草甚一ら16人の作家・評論家の著作とその背景を読み込み、それぞれ独特の思考の軌跡を追体験しようとする、実験的かつリスペクトに満ちた評論集。
目次
小林秀雄
田中小実昌
中野重治
武田百合子
唐木順三
神谷美恵子
長谷川四郎
森有正
深代惇郎
幸田文
植草甚一
吉田健一
色川武大
吉行淳之介
須賀敦子
福田恆存
著者等紹介
坪内祐三[ツボウチユウゾウ]
1958(昭和33)年、東京生れ。早稲田大学文学部卒。「東京人」編集部を経て、文筆家に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。