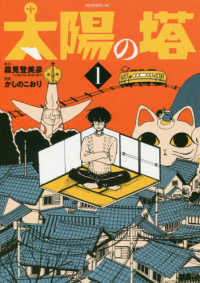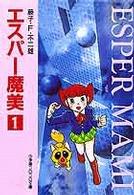内容説明
日本文化研究の若手No.1を自任する“気鋭のアメリカ人”が俳聖・松尾芭蕉の生涯を追跡し、芭蕉の真実の人間像に迫った…。青い眼のとてつもない誤解とコジツケが、読者の微苦笑や爆笑・哄笑を誘い、奇妙な芭蕉像が形づくられていく。カルチャー・ギャップから生れる誤解を過激な笑いに転じ、奇想天外の発想といく重にもたくまれた〈仕掛け〉で読者に挑むスーパー・フィクション。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
takaC
47
このセンス、好きだ。大好きだ。2013/06/02
阿部義彦
18
小林信彦さんの本は古本市では最初にチェックします。同工の『素晴らしき日本野球』は既に読んでましたが、より文学よりのこの作品の脱臼ぶりもぶっ飛んでます。芭蕉は忍者の末裔として、有るミッションを完遂する為に旅に出る。と思い込んだ外国人が書いた体の偏見にそれを翻訳した著者の訳注、二十三重のこじつけには爆笑。好きなのはジョンが俳句の影響で『マザー』でシンプルで深い詩作をしたのは真実らしいが、原注で「日本でジョンはホテルオークラと軽井沢に滞在したが、ポールは警察に滞在した。」文壇での孤立ぶりは橋本治と同じか。2024/05/14
瓜坊
16
日本文化の研究者フラナガン氏が語る芭蕉の足跡。という体裁のパロディ本。落語の「千早振る」のようにありえない解釈、こじつけで生まれるギャグ。ただ、自分で情けなく思うのは、パロディを読んで楽しむには真実の芭蕉知識が足りてないこと。知識がないとフラナガン氏みたいなヤツの語ることすら真贋を見抜けないという皮肉。奥の細道くらいはちゃんと読まないとダメですね。〈ワビ、サビも時にはワサビという形で括られる〉研究者という設定で、こんな調子のギャグが続く。俳句を無理矢理、違う解釈で見るという遊びは楽しそうな気がしてきた。2020/09/22
フリスビー
13
日本文化研究の若手No.1を自任する“気鋭のアメリカ人”が俳聖・松尾芭蕉の生涯を追跡し、芭蕉の真実の人間像に迫った…。はずなんですが、誤解に満ちた勘違いが笑わせてくれます。パロディ小説ですが、知的エンターテイメントとしても秀逸です。ひじょうに懐の深い作品ですね。2013/05/26
おとん707
9
アメリカの日本文化研究家W.C.フラナガンによる芭蕉の奥の細道を題材にした評伝Road to the Deep Northの小林信彦による邦訳本だがフラナガンの日本文化の理解度が著しく劣っており、誤解や早とちりが無数にある。それを訳者が丁寧に訳注で正しているがアメリカの知識人でもこの程度の理解かと苦笑を禁じ得ない。侘びと寂でわさびとか、柿食えばのカキは牡蠣だとか。雑誌掲載時にも書評で叩かれたそうだが、種を明かせばすべてが小林信彦の創作狂言。こんなハチャメチャな文学作品があろうとは。現在絶版なのが残念。2020/12/11