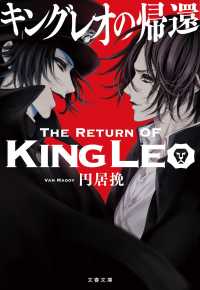内容説明
大阪の旧陸軍工廠の広大な敷地にころがっている大砲、戦車、起重機、鉄骨などの残骸。この莫大な鉄材に目をつけた泥棒集団“アパッチ族”はさっそく緻密な作戦計画をたて、一糸乱れぬ組織力を動員、警察陣を尻目に、目ざす獲物に突進する。一見徒労なエネルギーの発散のなかに宿命的な人間存在の悲しい性を発見し、ギラギラと脂ぎった描写のなかに哀愁をただよわせた快作。
著者等紹介
開高健[カイコウタケシ]
1930‐1989。大阪市生れ。大阪市立大卒。1958(昭和33)年、「裸の王様」で芥川賞を受賞して以来、「日本三文オペラ」「流亡記」など、次々に話題作を発表。’60年代になってからは、しばしばヴェトナムの戦場に赴く。その経験は「輝ける闇」「夏の闇」などに色濃く影を落としている。’78年、「玉、砕ける」で川端康成賞、’81年、一連のルポルタージュ文学により菊池寛賞、’86年、自伝的長編「耳の物語」で日本文学大賞を受けるなど、受賞多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
74
戦後、大阪の焼け跡で旧陸軍砲兵工廠跡の屑鉄を盗んで生計を立てているアパッチ族の生きざまを描く。頭が泥棒行為を正当化する理屈は、もちろん通るはずのないものなのだが、妙に的を射て現状を見事に揶揄っている。ぎりぎりのところで生きているアウトローたちの集団の中にある猥雑さ、むき出しのエネルギー、ひとつのことのみに集中する一途な生き方のすさまじさが圧倒的、しかも繊細な筆力で描かれている。2019/05/27
Shoji
55
昭和34年に上梓された本である。 大阪のジャンジャン横丁で路上生活をしていた主人公は、砲兵工廠跡からクズ鉄を盗むことを生業とする廃品回収業へと流れる。 生活は、醜悪、猥雑、無秩序、、、全てが最下層。 人間の最も基本的な活動である食べること、食べるためにすべきことに凄まじい執着を見せる。 開高健さんは、食べる臓物の臭い、汚染された運河の臭い、生活者の体臭、すえた部落の臭いまで再現してみせる。 開高健さんはこの物語で「生きることとは何か」を問いかけているような気がしてならない。2016/07/06
そうたそ
46
★★☆☆☆ アパッチ族ときくと、小松左京「日本アパッチ族」ばかりが思い出される。大阪の旧陸軍工廠の広大な敷地に転がる鉄材等に目をつけた泥棒集団アパッチ族たちを描く物語。この喧騒とした感じが大阪ならではのものと思う。発表された当時はまだ社会にもその面影が多少はあったのかもしれないこの作品も、今となっては遠い過去のようなものとなった。この喧騒とせせこましさがいいとは思わないが、この作品全体を貫くような生の力強さは圧巻。ただどうしても開高健の文章が自分には苦手に感じられる。何作か読んだがどうも慣れない。2016/07/04
reo
32
大阪造兵廠跡地から、鉄くずなどを回収し生計を立てる通称アパッチ族と、官憲との頭と体を使った鬩ぎ合い。これが無茶苦茶おもろい。彼らの食いもんやがフクスケの歓迎にあたってボスのキムが「えらいさしでがましいが、ひとつここはわいに奢らせてもらいまひよ」洗面器やバケツのなかに今には湯気がたつかと思えるほど新鮮な血と分泌物にまみれた牛の内臓が溢れていた。この日はほぼ牛一頭分の、食道から肛門に及ぶ内臓一式。ないのは角と皮と骨と普通の肉だけ。今では殆ど死語となった”ニコヨン””ルンペン”などの言葉が飛び交う。臨場感おま!2020/11/09
空猫
27
あらすじもよく分からず、ニコヨン、バタ屋…ググらないと分からない言葉や言い回しに不安になりつつ、でもその文章や世界観の熱量に惹かれ、読む。現大阪城公園、元は日本最大の兵器工場。その周りに一般社会からはみ出した者達の部落があった。放置された武器等の金属を掘り(盗み)出し、売り捌いて口を糊するのだ。バカとハサミは使い様と言うが、ここではどんな不具者も利用し、騙し騙され、ともかく男だけでなく女子供もたくましい!。お上なぞ当てにしないで庶民は助け合って(?)生きてきたんだよな。でもそれも一生続けられる訳もなく…→2020/05/13
-
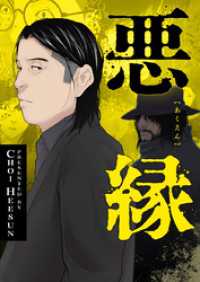
- 電子書籍
- 悪縁【タテヨミ】第30話 piccom…
-
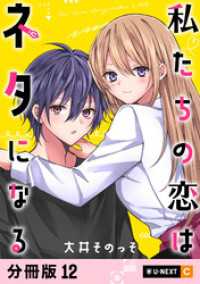
- 電子書籍
- 私たちの恋はネタになる 【分冊版】 1…
-
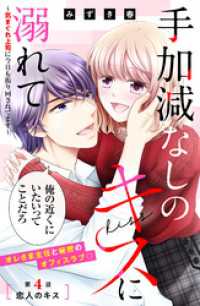
- 電子書籍
- 手加減なしのキスに溺れて~気まぐれ上司…
-

- 電子書籍
- 運転中ステイチューン(2) COMIC…