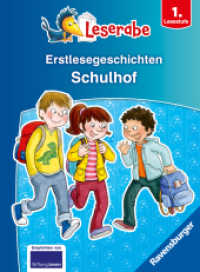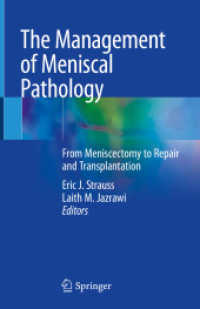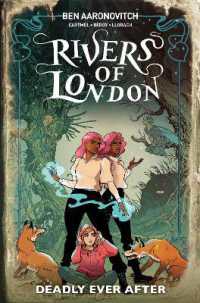内容説明
現在にとって未来とは何か?文明の行きつく先にあらわれる未来は天国か地獄か?万能の電子頭脳に平凡な中年男の未来を予言させようとしたことに端を発して事態は急転直下、つぎつぎと意外な方向へ展開してゆき、やがて機械は人類の苛酷な未来を語りだすのであった…。薔薇色の未来を盲信して現在に安住しているものを痛烈に告発し、衝撃へと投げやる異色のSF長編。
著者等紹介
安部公房[アベコウボウ]
1924‐1993。東京生れ。東大医学部卒。1951(昭和26)年、「壁」で芥川賞受賞。’62年発表の『砂の女』が読売文学賞、フランスの最優秀外国文学賞を受けた他、戯曲「友達」の谷崎潤一郎賞、『緑色のストッキング』の読売文学賞等、受賞多数。’73年より演劇集団「安部公房スタジオ」結成、独自の演劇活動を展開。’77年には米国芸術科学アカデミー名誉会員に推され、海外での評価も極めて高く、急逝が惜しまれる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件