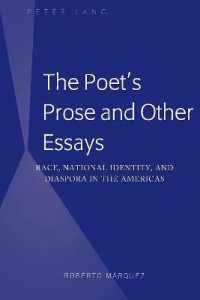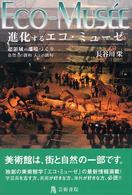内容説明
茨城県地方の貧農勘次一家を中心に小作農の貧しさとそれに由来する貪欲、狡猾、利己心など、また彼らをとりかこむ自然の風物、年中行事などを驚くべきリアルな筆致で克明に描いた農民文学の記念碑的名作である。漱石をして「余の娘が年頃になって、音楽会がどうだの、帝国座がどうだのと云い募る時分になったら、余は是非この『土』を読ましたいと思っている」と言わしめた。
著者等紹介
長塚節[ナガツカタカシ]
1879‐1915。茨城県生れ。正岡子規に師事。子規没後は同門の伊藤左千夫等と「馬酔木」を創刊、その教えを発展させるべく努力した。一方で写生文、小説も数多く発表し、長編小説『土』は夏目漱石の推薦で「東京朝日新聞」に連載された。農民文学の代表作といわれるこの作品の完成後、結核を病んだこともあって作歌の世界にもどり、晩年の優れた作品を残した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よむよし
114
話の展開や面白みを求める作品ではないです。土にまみれ欲望が渦巻く中を生き死んでいく農村の人達の日常を描いていきます。使われる当地の言葉は非常に読みにくいですがそうしないと作者の思いは伝わらないのでしょう。夏目漱石が寄せた『序』をオススメします。そこに「漱石といふ男は人を馬鹿にしている、と言って大いに憤慨していたそうだが、長塚君としては尤もの事である」とのくだりがある通り、歌人長塚節の姿勢は峻厳です。私にとっては「お前は人の役に立っているのか!」と叱咤してくれる教師のような本です。旧仮名遣いで読みました。2024/07/04
優希
104
農民小説として、リアルな風景を見ることができました。ドラマチックなことが起きるわけでもなく、小作人の貧しさを描ききった作品だと思います。与えられた場で命の営みをし、その時間を過ごしていく。それはある意味で農民の記録とも言えるのかもしれません。2017/03/05
ach¡
45
捕えられた憐れな昆虫をのぞき見るように、貧しさのなんたるかを観察する読書であった。明治の世が途方もなく遥けく思えるほど、あまりに現世とかけ離れた窮乏の世界がひもじい。もはや小説ではなく貧農の歴史記録。貧しさに足掻けば足掻くほど深みにはまり不幸が嵩む。人間の心がいとも容易く荒んでゆく哀しさとは対照的に、背景に広がる自然の営みが見目よい。地を這い、土を噛み、禍害にねぶられ、なお貧乏にしがみついて根を張らんとす彼らの生き様が惨めと殊勝を行ったり来たりするうち、憐憫の情よりも己の先祖を顧みるような感慨が先に立つ。2016/05/20
アナクマ
25
写実、農民文学の先駆け。漱石が推した新聞連載(娘が年頃になって浮ついたらこれを読ませたい、と言う)。明治晩期、茨城の鬼怒川沿い「彼と唐鍬とは唯一体である。刃先が木の根に切り込む時には彼の身体も一つにぐさりと其の根を切って透る」 ◉薪の確保が重要事。老婆は川の洲を掘りかえして木片を得る。日傭で開墾をする小作人がそこから得たクヌギの根株は警察に取り上げられる。境界木を切り倒して散った小枝や屑物すらもありがたい。(139)「冬毎に熊手の爪の及ぶ限り掻いて行くので、草も短くなって腰を没するような処は滅多にない」2025/08/09
モリータ
20
◆長らく積読だったが、環境の変化で全然読めてなかったのをこれはいかんと思い青空文庫+スマホで。◆これは一読では足りない。意外にも飽きないダイナミックな風景描写と、標準語訳なしでは意味のとりがたい方言会話、勘次の心理・行動の隠微さは、それらだけ追って読んでも面白そう。◆不十分な一読後に言えることとすれば、狭い社会で少ない資源を争う人物たちのさもしさ、陰ある者への揶揄や侮りの露骨さといった、現代でもそこここに見られる人間性の薄暗さの描写には心を打たれた。◆方言会話は宮島達夫先生による朗読と訳があるので心強い。2020/01/14