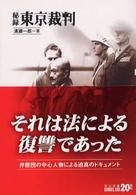出版社内容情報
珠玉。翻訳不可能と言われる融通無碍な美しさを極めた名文を、どうぞ。
明治37年の「菜の花と小娘」から大正3年の「児を盗む話」まで、著者の作家的自我確立の営みの跡をたどる短編集第一集。瓢箪が好きでたまらない少年と、それをにがにがしく思う父や師との対立を描く初期短編の代表作「清兵衛と瓢箪」、自分の努力で正義を支えた人間が、そのために味わわなければならなかった物足りない感じを表現した「正義派」など全18編を収録する。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
98
「小説の神様」と称される志賀直哉。確かにそう言われるであろうと思われる名文でした。高い写実力と表現が美しい。日常の機微を切り取る手法が鮮やかです。処女作を含むのみならず、作家的自我を確立させた短編集。初期から評価の高い作品を描く直哉の短編に対する手腕に驚かされるばかりです。2016/09/15
サンタマリア
48
志賀直哉が尾道にいたと言う話は聞いたことがあったけど、その理由までは知らなかった。知った上で表題作『清兵衛と瓢箪』を再読すると、若い青年の意地のようなものを感じた。「こういうのがええんじゃ」。『襖』の歯痒さが好きだから、解説で最後の一文で友と私が重なると教えてもらった時は、なんだか自分のことのようにくすぐったい気持ちになった。2023/07/03
ω
39
著者の作家的自我確立の営みだそーなω 「濁った頭」「正義派」「清兵衛と瓢箪」がよかった。 しっかし、お金持ちの家でぐうたらしててオコされて、引っ越そうとして「やっぱやーめた」って帰ってきたり、何かこの主人公きらーい笑! 志賀直哉とバトルしまくってた作家先生多いのちょっと分かるww2025/06/28
メタボン
36
☆☆☆☆ 網走まで行く列車の中での母と赤子との交流が心に残る「網走まで」が特に良かった。ナイフの芸の際に妻を殺してしまう「范の犯罪」の緊張感は、「剃刀」と対をなす。列車に子供が轢かれるという点で「出来事」と「正義派」も対をなす作品。2023/03/23
カブトムシ
33
「正義派」…大正1年9月『朱樂(ザンボア)』に発表。「車夫の話から材料を得て書いたもので、短編らしい短編として愛している。」(「創作余談」)ある夕方日本橋の方から永代橋を渡って来た電車が、橋を渡るとすぐの所で、湯の帰りらしい二十一、二の母親に連れられた五つばかりの女の児を轢(ひ)き殺した。「警察での審問は割に長くかかった。運転手は女の児が車の直ぐ前に飛び込んで来たので、電気ブレーキでも間に合わなかった、と申し立てた。工夫等はそれを否定した。狼狽して運転手は電気ブレーキを忘れていたのだ、…といった。…」
-

- 電子書籍
- CGWORLD 2020年7月号 vo…
-

- 和書
- 犬に贈るラブレター