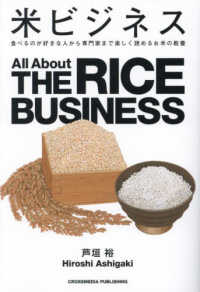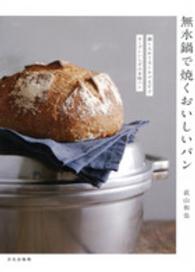出版社内容情報
〈夢読み〉として幻想の街にとどまるのか、〈影〉を取り戻して壁の外に立ち戻るのか――孤独な心を抱えながら現実世界で四十五歳になった主人公の「私」は、ある夜の夢に導かれ、会津の山間(やまあい)の小さな町に向かい、図書館長の職に就いた。ベレー帽にスカート姿の前館長子(こ)易(やす)老人の幽霊、〝街〟の地図を携えた〝運命の少年〟の出現……魂を深く静かに揺さぶる村上文学の迷宮へ。
内容説明
図書館のほの暗い館長室で、「私」は「子易さん」に問いかける。孤独や悲しみ、“街”や“影”について…。そんなある日、「私」の前に不思議な少年があらわれる。イエロー・サブマリンの絵のついたヨットパーカを着て、図書館のあらゆる本を読み尽くす少年。彼は自ら描いた謎めいた“街”の地図を携え、影を棄てて壁の内側に入りたいと言う―二つの世界を往還する物語がふたたび動き出す。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





読書という航海の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
129
やっと上下巻を読むことができました。村上さんの作品は初期のころの短篇やエッセイ集をかなり読んでファンでした。いつ頃か疎遠に合ってしまっていて長編も「海辺のカフカ」は何度か読んでいました。ただやはり村上さんの長編は合わないようです。この本も現実と異世界のような感じの場面があったりして構成としては面白いのでしょうがどうも、という感じです。図書館がらみの場面は興味を引いてくれました。そのうちじっくりと長編に手を付けていこうかと思っています。2025/07/25
シナモン
91
読み始め苦戦した上巻とは打って変わってするすると読めました。福島の図書館の雰囲気がとても好き。そこでの丁寧に紡がれる主人公の日常の描写にも惹かれます。幻想的な部分よりそういうところに引き込まれました。2025/11/11
nobi
78
上巻では現実的にありえないと思っていた状況が、下巻では見知った世界として展がってくるよう。引用もあるガルシア・マルケスの描写が非現実でありながらリアルに感じるのとは違って、凍りつくような悲劇の場面を除いては、薪ストーブに焚べる林檎の古木の香りもマフィンの味も、子易さん添田さん女性少女少年の風貌も彼らとの会話も、現実なのか夢なのか定かでない。言葉の様相は変わらず優しく身に沁みる。また他とのコンタクトが限定的な人も静かに相手に気遣っているという関係の優しさにも気付く。ただ最後まで壁って?影って?の謎は解けず。2025/05/30
ふう
71
この作品に登場する人々はみな「不思議な存在」です。主人公の私、死んでいるのに姿を現す前図書館長、特別な能力をもつ少年。普通に見える人にも他人からはおしはかれない過去や思惑があり、壁の中に住む人と外に住む人は、どちらが実体でどちらが影か問いかけられているようです。中に住む人は静かにおだやかに暮らしていて、外に住む人は悲しみや苦しみが多そうです。それでも見える世界しか認識できないわたしは、壁の中に入っていった少年が今はきっと幸せなのだろうなと思いながらも、こちらで頑張るしかないのですが。おもしろい作品でした。2025/08/04
歩行者天国
52
良い作品は何度読んでも面白いのです。下巻はイエロー・サブマリンの少年が大活躍なのです。少年は壁の街の地図を描くのですが、その地図は「世界の終り~」に付いてる地図と同じものなのでしょうか。それにしても、壁の外の世界に戻った「私」とコーヒーショップの女性が、その後どうなったのかが気になるのです。2025/06/18