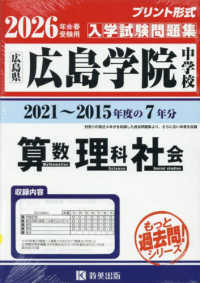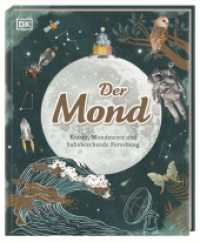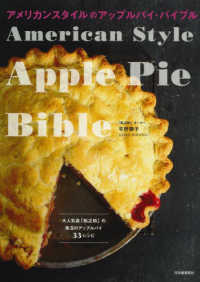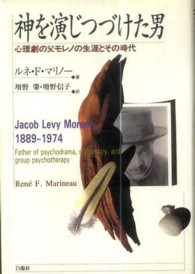出版社内容情報
実践例を基に「教師の有りよう」を考える。
本書は、世阿弥の「風姿花伝」において、「態(わざ)」と表現された「身と心の構え」とそこから得られる学びに沿い、教師の授業実践とその学びはどのようにあるべきか、について著していくものである。これまで授業技術について書かれた書物は多いが、そのほとんどは授業技術を教師に伝える「指南書」であった。それらとは一線を画して、教師の「学びの思想」や「身体技法」を伝える「花伝書」として、佐藤教授がこれまで観察してきた教室の実例に即して叙述していく。
「教師の教師」としてカリスマ的に支持されている佐藤学氏久々の決定版!!
佐藤 学[サトウ マナブ]
著・文・その他
内容説明
「風姿花伝」の精神に沿い、教師の授業実践とその学びのありようを探る。
目次
第1部 専門家として成長するために(教師として学び成長すること―花伝書からの啓発;創造的な教師の技法―授業の「妙花」を開く;教師の居方(ポジショニング)について ほか)
第2部 私の出会った教師たち(小学校低学年の文学の授業;高校を変える校長のリーダーシップ;授業の事実が見えるということ ほか)
第3部 教師として生きる(教師が専門家として育つ場所;授業の事実から学ぶこと;教師として尊重すべきこと ほか)
著者等紹介
佐藤学[サトウマナブ]
1951年広島県生まれ。教育学博士、東京大学大学院教育学研究科教授。全米教育アカデミー会員、アメリカ教育学会名誉会員。日本教育学会会長、日本学術会議会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- CD
- 小椋佳/眦(まなじり)