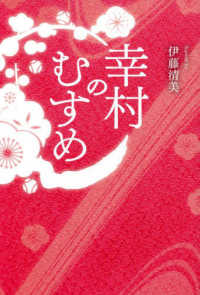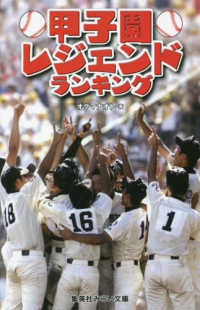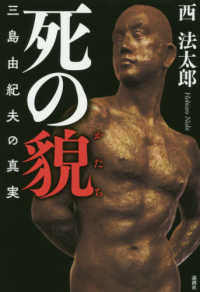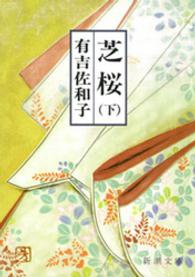出版社内容情報
常滑焼は、遺跡の年代決定の指標であるとともに、中世史を解く鍵である。発掘担当者・考古学者・歴史学者らによる学際的なシンポジウムをもとに、編年や生産・流通・消費などの問題を考察し、中世社会の実像に迫る。
中世常滑焼は、東北地方から九州まで全国各地で広範に発掘されており、遺跡の年代をきめる指標として、重要になっている。そこで、その編年や生産体制の問題が、現在大いに注目を集めている。さらに、流通経路やそれを運んだ船と海路の問題、使われ方の問題、生産・流通にたずさわった人々の実像などについても、きわめてビビッドな研究が進められており、一般の歴史・考古学ファンにも興味深いテーマとなっている。 本書は、日本福祉大学知多半島総合研究所主催で、地元の研究者・中世考古学の専門家・中世史学者などを一堂に集めておこなわれた学際的なシンポジウム「中世常滑焼を追って」をまとめたもので、中世史の鍵といえる常滑焼について、多方面の最先端の研究成果がわかりやすく語られている。 本書の編集にあたって、概説的な部分を加え、多数の写真・図版を収録したことによって、専門外の読者にも読みやすく楽しめるものになっている。また、最新の編年表を巻末折り込みに収録、発掘担当者にも必携の本である。
目次
第1部 中世常滑焼の実像―技術・生産・編年(中世常滑焼とは何か;生産地における編年について;山茶碗の生産体制;十二世紀の常滑窯の瓦生産窯 ほか)
第2部 広がりゆく常滑焼―分布と流通形態(奥州平原にみる常滑焼;東国の常滑焼の出土状況;西国の常滑焼の出土状況;東国における常滑焼の流通と消費 ほか)