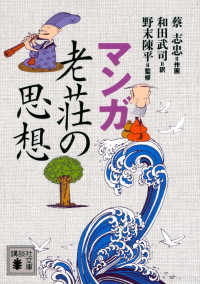出版社内容情報
驚異の築城技術が、写真と図解でよくわかる
大好評を博した小学館ウイークリーブック『名城をゆく』から生まれた城図典の決定版。城郭史研究の第一人者が、城づくりの知恵と技術、秘められた謎を解き明かします。 縄張の仕方、堀や石垣のつくり方、天守や御殿の建て方、城下町のつくり方など、城づくりのプロセスを追いながら解説していくわかりやすい構成。400点もの写真と160点もの図版で、細部の構造までよく理解できます。また、著者による安土城復元図(立面図・断面図)をはじめ、城の発展を主要城郭の復元図でたどる口絵もつきます。 本書を片手に城をめぐれば、気分はたちまち一国一城の主となれるでしょう。あなたの城の見方を一新する、歴史ファン、城ファン待望の城図典です。
内容説明
写真約380点、図版約160点を掲載。城地の選び方、石垣・天守・御殿などの築き方から、城下町のつくり方まで、「城をつくる」すべてがわかる。
目次
1 縄張の章(城地を定める;曲輪を築く ほか)
2 普請の章(堀をうがつ;上塁を盛る ほか)
3 作事の章(天守を上げる;櫓を上げる ほか)
4 城下町の章(城下町の役割;街道と港をつくる)
5 城の歴史と地方色(城の歴史;城の地方色)
著者等紹介
三浦正幸[ミウラマサユキ]
1954年生まれ。広島大学大学院文学研究科教授。東京大学工学部建築学科卒業、工学博士。一級建築士。専門は日本建築史および文化財学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
6
戦国時代、信長を頂点とした頃、安土城の豪華さが目を見張ったという。建立後3年で焼失した安土城を図版で見られるのは素晴らしい。信長の後継者となった秀吉は、安土城の豪華さを継承し大阪城を築いた。不整形で複雑すぎる形状は改善され、これがのちの天守の手本となった。江戸時代を通じて幕藩体制維持の象徴とされていた近世城郭は、明治維新で不要となり、維持費の莫大さを理由に、明治7年から次々と破却。同じころの廃仏稀釈で消失した仏教関連資料や施設と同様、惜しまれる。その大半が、薪として売却され取り壊されたのが残念でならない。2021/08/04
piro5
6
城の作り方が、その目的を明らかにしながら詳細に説明される。軍事目的なので、1つ1つに防御の目的がある。それがわかる。後半の説明からは図が不足しているため、それが残念。でもイイ。2013/10/27
Junpei Ishii
5
書かれている内容は、近世城郭を対象としています。 単なる城郭ガイドブックだと、櫓と天守閣、門などの構造物ばかりが紹介されているケースが多いのですが、縄張りとその軍事的な意味についても十分に解説されているので、入門書として非常に適切でした。 もちろん、天守閣や門などの構造物についても十分な記述がありますし、通常城郭本では扱われることの少ない御殿の構造についても言及されている点がすばらしいと思いました。2012/09/02
ponnelle
4
この一冊があれば一から築城出来そう。しないけど。2017/09/08
siomin
4
城の構造について解説した本ですが、図版が多く城の構造を網羅しており、初心者からベテランまで満足できる1冊です。著者の書きぶりで注目すべき点は、築城技術は江戸時代初期までが最上で、それ以降は劣っているという見方。江戸軍学を基にした築城術は所詮机上論で実践に役立つものではなく、昭和時代の築城ブームで作られたモルタルやコンクリート製の城は強度において近世に作られたものに及ばないそう。だからこそ、貴重な城跡は残していかないといけませんね。2015/12/20