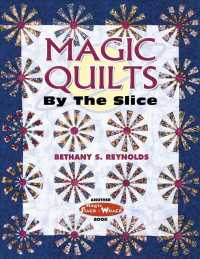- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
出版社内容情報
脳が活性化する運動療育、日本家庭に初上陸
◆「スパーク運動療育」とは?
→特性をもつ子の「脳の発達」「新しい脳神経をつなぐこと」を目的とした運動療育。
◎子どもの興味を生かしながら子どもの意思で楽しくからだを動かし遊ぶという療育で、すでに発達障害の見られる何百人もの子ども達の改善効果が報告されています。
◎ハーバード大学レイティ博士監修のもと、清水貴子氏が具体化・開発をし、日本に通所支援事業としてスタートさせています。これを家庭でもできるように、と初めて書籍化したのが本書です。
◆改善例さまざま。どの子も3か月で変わる。
↓
◎小6男児/入学して分かった対人感覚が個性的で友達の輪に入れない状況。発達精神科通院の後、紹介され、この運動療育を4年生から開始。初日から瞳が輝き笑顔に!最近はクラスの子と行動出来るようになった。
◎小5女児/1年も経たずに表情が改善。人の気持ちを考えられない子だったのに笑顔が増え「ありがとう」が言えるように。学校も楽しく友達もできた。
◎小2男児/苦手な運動はしない、自己主張の強い子だった。スパーク運動療育1回目で、一段ずつ足を揃えてしか降りられなかったのに早くも駅の階段を普通に降りられるように!自己肯定感が高まり挑戦できるように成長。
【編集担当からのおすすめ情報】
<運動機能>からだを動かす、
<感覚>五感を使う・刺激する、
<感情>感情に働きかける
子どもの成長の、この3つの”根っこ”に働きかけるスパーク運動療育。
人間の「脳力」は、これでたくましくなる、と
体験した子ども達の様子を見て痛感しました。
「学習能力も高まる」というのも、
腑に落ちます。
内容説明
大切なことは、子どもが体を動かすようにすること。不安でも大丈夫!3か月で変わります。家庭でできる運動あそび78。
目次
第1章 発達障害の子の脳をきたえるには運動がいちばん!(運動すると、学力が上がる!;運動すると、脳細胞が増える!;発達障害の子の脳に新しい回路ができる! ほか)
第2章 家庭でできる運動あそび78(走るの大好き!;高くジャ~ンプ!;リビングであそぼ! ほか)
第3章 パパ、ママこそ療育士になれる!家族の心がまえ8か条(まずは大人が自ら率先して遊ぼう;興味につきあい、発展させる;感覚のキャパシティを広げる ほか)
著者等紹介
清水貴子[シミズタカコ]
一般社団法人日本運動療育協会理事。「EQを鍛える身体ワークショップ」主宰、舞踊家。1962年大阪生まれ。幼少の頃からダンスを始め、18歳でダンス・カンパニー「WITH」を立ち上げる。その後、上京してソロの舞踊家として数々のステージに出演。レイティ博士との出会いから脳の発達を促すさまざまなトレーニングプログラムを開発し、発達障害児の改善、企業に働く社員のうつ予防、高齢者の認知症予防などを目的に幅広く指導している
レイティ,ジョン・J.[レイティ,ジョンJ.]
ハーバード大学医学大学院精神医学准教授、臨床医。医学博士。一般社団法人日本運動療育協会特別顧問。1980年代にエドワード・ハロウェル医師とともにADHDの研究を始め、94年にはじめてこの障害をわかりやすく解説した本『へんてこな贈り物』を出版。2008年にはアメリカでベストセラーとなった『脳を鍛えるには運動しかない!(原題/SPARK)』を出版。現在、ボストンで医療に携わるかたわら、非営利団体Sparking Lifeを主幹
ナムーラミチヨ[ナムーラミチヨ]
絵本作家。1948年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。