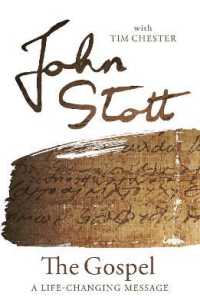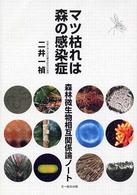内容説明
名作『不滅』を発表したあと、クンデラは《ランフィニ》誌にほぼ毎号エッセーを書きつづけていた。あるときにはカフカ、ヤナーチェクといった小説家、音楽家について書き、あるときにはラシュディ、シャモワゾらの南方作家の擁護のために筆をとった。さらにベルリンの壁の崩壊、チェコスロヴァキアのビロード革命、ソ連解体という、歴史の急速な大変化をまのあたりにしながら、フランスに住む東ヨーロッパ出身の小説家として言いたいこと、言うべきこと、言えるようになったことを冷静で透徹した考察の形で発表した。
目次
第1部 パニュルジュがひとを笑わせなくなる日
第2部 聖ガルタの去勢の影
第3部 ストラヴィンスキーに捧げる即興
第4部 一つの文章
第5部 失われた現在を求めて
第6部 作品と蜘蛛
第7部 一家の嫌われ者
第8部 霧のなかの道
第9部 きみ、そこはきみの家ではないのだよ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
39
これ程までに多弁で、こんなにも情熱的なクンデラが他にあっただろうか。傑作『不滅』執筆後に書かれたエッセーをまとめた本作では、芸術とは決して不滅のものではなく、その通俗的な側面のみ普遍的なものとして残されてしまう前作の主題に徹頭徹尾、抗おうとしている。カフカとヤナーチェクというチェコの代表的芸術家である二人を中心としながら、ここにあるのは時に作家至上主義に見えてしまう不器用なクンデラの姿だ。それはいつになく隙だらけでありながら、だからこそ時代の、歴史の、芸術の困難さを語ろうとする力に満ち溢れているのだ。2014/10/08
原玉幸子
20
『存在の耐えられない軽さ』のM・クンデラのエッセイですが、彼が網羅言及する分野や時代や例示する芸術家に馴染みがないからか、字面だけを追って、理解出来なかった章もありました。音楽を解説して「小説たるもの」に理論付けるところは、「おぉー、芸術の真髄!」と思える箇所もありましたが、難解と言うより喩えや構成が読み難く、全編を通じてはタイパで首を傾げる印象でした。表題に繋がるカフカの評伝挿話が抜群に面白いので、その章だけで本にしてくれれば良かったのに。(◎2023年・冬)2023/11/18
34
19
作家の私的生活を擁護して、クンデラはカフカの遺言は真に受けられるべきだったという。しかしカフカに関して、その断片すべて、その生の片鱗すべてにいたるまで価値がある、と感じることは、古い文学観に属することだろうか? ある種の作品主義(作家の実存を括弧に入れること)は、キッチュの最高度の蔓延とともにすでに死に瀕しているのだとしたら?2019/07/17
美東
14
Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%88 によると、(カフカの友人である)”ブロートはカフカの遺稿の管理人となった。カフカ自身は遺言ですべての遺稿を焼却するようにとブロートに頼んでいたが、ブロートは自己の信念に従い、生前未発表であった(中略)カフカの遺稿を次々と公刊していった。”「裏切られた遺言」である。2023/02/25
パオー
9
さすがの面白さ。他の評論よりも音楽家とカフカについての記述多め。個人的には「友達」について考えさせられた。カフカの遺言を裏切って遺作を出版したマックス・ブロートは、カフカのことを神のように崇拝していたが、その芸術的真価を正しく理解してはいなかった。カフカはブロートに才能がないことを知っていながら、唯一の親友として彼を愛した。クンデラは言う。「だが、あなたがたは親友がしょっちゅう下手な詩を書くからといって、その親友が好きでなくなるだろうか?」しかしブロートの無理解のために、カフカは誤解され続けることになる。2013/03/07
-
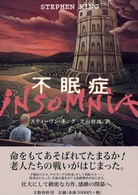
- 和書
- 不眠症 〈下〉