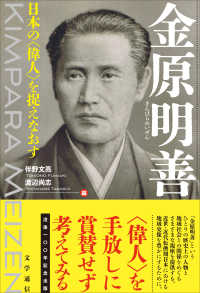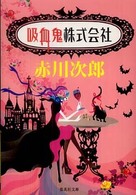内容説明
1999年のNATO軍の空爆により、コソボ紛争は公式には「終結」したことになっている。しかし現地では、セルビア系の民間人が三〇〇〇人規模で行方不明になるなど、空爆前とは違った形で「民族浄化」が続き、住民たちは想像を絶する人権侵害の危機にさらされている。また、空爆による劣化ウラン弾の被害は甚大で、すべての回収には一〇〇年を要するという。本書は、空爆終了後六年間にわたって現地に通い続けた唯一のジャーナリストが、九・一一やイラク戦争の開始以降ほとんど報道が途絶えてしまったセルビア・モンテネグロの現状を告発した、渾身のルポルタージュである。
目次
第1章 大コソボ主義(二〇〇一年~二〇〇二年)(消えた一三〇〇人―セルビア人拉致被害者たち;真っ先に見た事務局長 ほか)
第2章 混迷の中で(二〇〇二年)(劣化ウランとユーゴスラビアの核;一〇月革命の裏側)
第3章 セルビア・モンテネグロの誕生(2003年)(新憲章発布とモンテネグロ;新憲章発布とコソボ ほか)
終章 語り部(二〇〇四年一〇月)(コソボ紛争終結後、最悪の暴動;スミリャネ―「民族浄化」された村にて ほか)
著者等紹介
木村元彦[キムラユキヒコ]
1962年愛知県生まれ。中央大学文学部卒。ノンフィクション・ライター、ビデオ・ジャーナリスト。疾走プロダクションを経てフリーに。アジア・東欧の先住民族問題を中心に、「Number」や「PLAYBOY」などに数多くの記事を寄稿
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
32
「コソボ 苦闘する親米国家」をきっかけに著者過去作に。NATO空爆が一段落、あまり報道されなくなった2000年前後のバルカン情勢の混乱を、自ら現地に赴いての半端ない取材で、大手マスコミでは困難と思われる迫力リポート。アルバニア人とセルビア人の確執、ボスニア・ヘルツェゴビナの混乱、(北)マケドニア戦争、セルビア北部のボイボディナ州とハンガリーの関係、知っていること知らないと含めて刺激的読書時間が得られる。環境により人間は仏にもなり鬼にも私も貴方も。その原因を詰めるための読書でもあるかも知れない。2024/09/16
林 一歩
20
ジェノサイドについて、もう一度考えたいとの思いから再読。2015/02/08
ちくわん
18
2005年6月の本。ユーゴ紛争。紛争に紛れて行われた「民族浄化」と呼ばれた殺人・略奪・破壊。バルカンの火薬庫と呼ばれた地域に現在も存在する混沌。なぜ、地球に平和は続かないのか?それにしても彼らが日本のことをよく知っていることに驚かされる。この事実を覆すことが課題だ。勉強になった本。2020/02/10
MILKy
16
【売】2005.2019.いつになく難しめな本を手に取る。ユーゴスラビア。学生の時に耳にしたことがある国名。当時、マスメディアからもコソボとかボスニア戦争、?とか、サラエボ⋯と単語としては耳に入っていたけど、世界史の教科書に入るほど古い話でもなかった。そこでそのあたりの事情を知りたかったので手に取るもルポタージュで、知ったうえで読んだ方が良さそうな発展編な内容だった。書き方は口語で難くはなかったのだけど。あれなのかな、セルビアって世間的に悪者扱いされてるけど、それが全てではないってことが言いたかったのかな2023/09/29
おおた
14
暴力が発露する前になんとかならなかったのかという無念さばかりが残る。セルビア空爆から数年、各民族の生の声を届けてくれる希有な本だけど、もう少し歴史的なまとまりを把握した上で手に取るべき本だったかも。ヨーロッパの火薬庫と呼ばれたバルカン半島が民族によってこれほどの憎悪を抱くようになってしまったのかは明確に語られない。一方で各民族は、地域を牛耳ると敵対する民族の一般人を拉致して殺害する。敵だから殺すという感情の問題と、大国からの武器供給による戦闘の長期化は、どれだけの人の血を流せば終わるのだろうか。2017/11/18