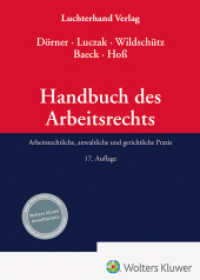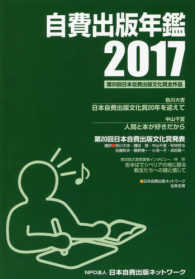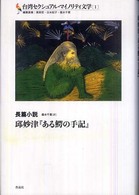内容説明
広島市の小学校の、剥げ落ちた壁の奥に、白墨で書かれた伝言が見つかった。それはかつて原爆資料館にも展示されていた菊池俊吉氏撮影の「被爆の伝言」写真の、その原物が、二〇世紀の末になって再び人々の前に現れた奇跡の瞬間だった。著者はNHK広島放送局のディレクターとして取材を始める。一九四五年八月、辛うじて倒壊をまぬがれた袋町国民学校は、被災者の救護所として使用された。安否をたずね、消息をしらせる短い伝言。長い年月を凌いできた縁者が、初めて直に伝言に向き合う一瞬。半世紀を経て蘇る「あの日」。覇権とテロのせめぎあう時代に、改めてヒロシマを問う。
目次
序章 重なった奇跡
第1章 写真家が見たヒロシマ
第2章 幻の姉に出会えた
第3章 児童を殺した教師たち
第4章 新発見、迷路をたどるように
第5章 親と子
第6章 伝言との対面
第7章 そして残されたもの
終章 テロと戦争の時代に
あとがき 三年後の出来事
著者等紹介
井上恭介[イノウエキョウスケ]
1964年生まれ。87年東京大学法学部卒業、NHK入局。静岡放送局、報道局番組部等を経て、広島放送局報道番組ディレクター。中華五千年の至宝から歴史をひもとくNHKスペシャル「故宮」、政権幹部への取材から百万人をこえる自国民を殺したカンボジア、ポル・ポト政権の謎に迫るNHKスペシャル「ポル・ポトの悪夢」を制作
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
汐
57
図書室本。ヒロシマの壁に残された伝言。それを見た家族が流す涙は原爆の悲しみや苦しみではなく感動の涙だった。家族が家族を探し、先生が教え子を守るために残した伝言が、戦後半世紀以上経った今、全く別の意味を持ち語りかけている。実際に被爆したわけでもなく、戦争体験を聞いて育ったわけでもない若い人達が、その感動を理解するには想像力が必要。家族を探し回り、見つからない悲しみが残した伝言。難しいけれど、想像することが原爆を遠い過去にしない為にできることだと思います。資料館で実際に見てみたいです。2016/09/23
へくとぱすかる
40
広島の小学校の壁に残されていた、被爆直後にチョークで書かれた伝言。50年以上の歳月をへて、最新の技術を駆使しても読めない文字が、家族には判読できたという。関係者が、「あの日」の、消えてしまった肉親の痕跡を求めるさまは、原爆のもたらした被害、悲惨さが、今も決して薄れることのないことを、如実に物語るだろう。平和学習にきた小学生に、著者は自分の好きだった家族が突然いなくなること、どこかで生きていてほしいと伝言を書くことがどんな気持ちなのだろう、と語ったそうである。袋町小学校の資料館をぜひ一度訪れたいと思う。2015/08/03
井戸端アンジェリか
18
9.11の沢山の貼り紙を想像してみる。あの紙は一体いつまであそこに貼られていたんだろうか。誰が剥すのか、見つかったら剥すのか。戦時中の日本に紙は豊富にあったんだろうか。多分今のようにはない。あってもあの場所にはない。全て焼き尽くされてしまったから。 生まれ変わりのように誕生した妹さんが「ああ、お姉さんに出会えた」と喜び、知らないはずの母の字なのに懐かしさがこみ上げてくると語る、あの日で孤児になった女性。伝言の関係者の方々がほぼ喜んでくれる事に良かったねと泣いた。手書きの文字はずっと生きているんだね。2018/08/05
はーこ
11
広島や長崎は原爆投下の日が出校日だったり、終戦の日にサイレンが鳴ったりと今も次世代へ戦争の悲惨さを伝える活動がきちんと行われている気がするけど、それ以外の県は夏休みにあまり戦争を取り上げることもない。昔はあった戦争のドラマもなんだか最近中身が薄く感じるのは自分のせいなのか…。壁の伝言からその時がどんな状態であったのか、被爆者、その子孫たちの話を読んで、胸が詰まった。2015/08/30
jj
6
2003年著。爆心地からわずか460メートルに位置する小学校(袋町小学校)の壁に残されたメッセージ(白墨)を丁寧に検証していく内容。肉眼では判定しにくいものも、可視光線、赤外線処理などを駆使し解読に成功。被爆直後の家族・知人が行方不明の身内を捜し求める生々しい状況が目に浮かぶ。メッセージを検証することにより明らかとなった特定者のそれぞれのエピソードは胸を打つ。遺族に対する慰みとともに被爆地における資料的価値のある内容であり、とても興味深く拝読させてもらいました。2016/08/07
-

- 電子書籍
- ようこそ、私のキッチンへ 分冊版 Pa…
-
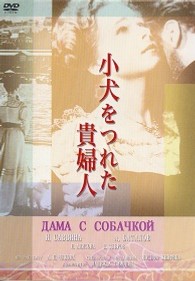
- DVD
- 小犬を連れた貴婦人