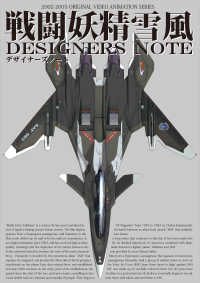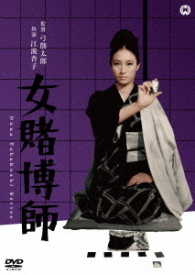内容説明
多くの日本人にとって、ブラックボックスのような存在、それがイスラムではないだろうか。イスラム過激派によるテロ活動や、バーミヤン石仏の破壊などで「イスラムは怖い」という印象を持つ人もいる。だが、イスラムとはもともとサラーム(平和)というアラビア語から派生したことからもわかるように、平安と平等を求める宗教なのだ。グローバル化の現在、12億人の人々が暮らすイスラム社会への理解なしに、われわれは世界を語れない。本書は、イスラムの歴史や思想、そして現代イスラムの潮流を、わかりやすく読み解く格好の入門書である。
目次
第1章 イスラムとは何か
第2章 イスラムの宗派と、民族の融和と抗争
第3章 成長する「イスラム原理主義」とは何か
第4章 パレスチナ問題―イスラムと異教徒との最大の紛争
第5章 現代の「ジハード」をスケッチする
第6章 イスラムとの共存・共生を考える
著者等紹介
宮田律[ミヤタオサム]
1955年、山梨県甲府市生まれ。慶応義塾大学大学院文学研究科修士課程修了。カリフォルニア大学ロスアンゼルス校(UCLA)大学院歴史学科修士課程修了。現在、静岡県立大学国際関係学部助教授。専攻は、イスラム地域研究、国際関係論。イスラム過激派の活動とイデオロギーの解明をテーマに、多くのイスラム国・地域を取材
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。