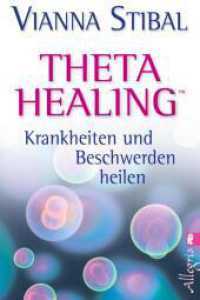出版社内容情報
問「仏とは何ぞや」
答「三斤の麻」
一見ちんぷんかんぷんなこの問答。禅問答とはこのように不可解で、それを考え抜くことこそが修行だと思われてきた。しかし、問答が生まれた唐代の文脈に戻すと、思いがけないほど明晰で合理的なやりとりが立ち上がってくる。「ありのままで仏であり、仏性とともに躍動し、己れの外に何ら求める必要のない自己」を説いた臨済の生きたことばが、今あざやかによみがえる!
唐代の禅僧、臨済義玄(?―866 / 867年)のことばを集めた『臨済録』は、我が国の臨済宗では「録中の王(語録の王)」とも称されてきた。しかし「聖典」となる以前、『臨済録』が本来伝えようとしたものは何だったのか。有名な「仏に逢うては仏を殺し、祖に逢うては祖を殺す」は、何を意味しているのか。
夏目漱石や西田幾多郎、鈴木大拙など明治以降の知識人にも愛好され、欧米社会に輸出されて今やZENとして広く愛好されている禅理解は、いかなる解釈も受けつけぬ問答を旨とする宋代禅を起点としている。活気ある唐代禅から深淵な宋代禅へのダイナミックな転換、さらに日本の近代禅に続く禅問答の思想史を踏まえたうえで原典に向き合ったとき、『臨済録』の世界が了解可能な経験として、その豊かな姿を現し始める――。唐代禅の重要な特徴は「激烈な聖性否定の精神が、平凡な日常性の肯定と表裏一体になっている」ところにあると著者は言う。
いきいきとした現代語訳で、臨済のやりとりが目の前で繰り広げられているかのように、あざやかに描き出される。清新な語録の世界!(原本:『『臨済録』――禅の語録のことばと思想』岩波書店、2008年)
【本書の内容】
プロローグ――古典としての禅語録
第1部 「柏樹子」の思想史――書物の旅路
第一章 唐代の禅
第二章 宋代の禅――圜悟と大慧
第三章 『無門関』から日本近代の禅理解へ
第2部 『臨済録』導読――作品世界を読む
第一章 臨済の説法
第二章 事(じ)已(や)むを得ず――臨済院の説法
第三章 傍家波波地(ぼうけははじ)――自らを信じきれぬ者たち
第四章 未だ見処(けんじょ)有らざりし時――若き日の臨済
第五章 仏法無多子(むたす)――黄檗との因縁
第六章 ふたたび「祖師西来意」――祖仏と別ならず
第七章 無事(ぶじ)是れ貴人(きにん)――修行の否定と平常無事
第八章 無位の真人(しんにん)
第九章 空中の鈴の響き――臨済と普化
エピローグ――鈴木大拙と二〇世紀の禅
内容説明
唐代の禅僧、臨済義玄のことばを集めた『臨済録』。「録中の王」とも称されてきた禅門の聖典だが、「聖典」となる以前に、この書物が伝えようとしたものがある。当時のことばと思想史に即して読みなおした時、「ありのままの汝こそが仏である」、そう迫ってくる臨済の活きた肉声がよみがえる―。清新な現代語訳が拓く、躍動感あふれる禅の語録の世界!
目次
プロローグ 古典としての禅語録
第1部 「柏樹子」の思想史―書物の旅路(唐代の禅;宋代の禅―圜悟と大慧;『無門関』から日本近代の禅理解へ)
第2部 『臨済録』導読―作品世界を読む(臨済の説法;事 已むを得ず―臨済院の説法;傍家波波地―自らを信じきれぬ者たち;未だ見処有らざりし時―若き日の臨済;仏法無多子―黄檗との因縁;ふたたび「祖師西来意」―祖仏と別ならず;無事是れ貴人―修行の否定と平常無事;無位の真人;空中の鈴の響き―臨済と普化)
エピローグ 鈴木大拙と二〇世紀の禅
著者等紹介
小川隆[オガワタカシ]
1961年生。駒澤大学大学院仏教学専攻博士課程満期退学。博士(文学)(東京大学、2009年)。駒澤大学総合教育研究部教授。専門は中国禅宗史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
さとうしん
黒い森会長
Go Extreme
-

- 電子書籍
- アナタのアイドル~冴えない俺が執着され…