内容説明
徳田秋聲、正宗白鳥、葛西善藏、宇野浩二、嘉村礒多ら地方出身作家が「東京」を舞台に紡いだ私小説、永井荷風、谷崎潤一郎が描いた戦後日本人の原像―。日本近代文学における「東京物語」の系譜をたずねて、書かれ、読まれ、生きられた重層的な時間を往還し、現代人の出自をたどる連作エッセイ。後期作品群への扉をひらく「決定的な重要性を持つ問題作」(松浦寿輝)。
目次
安易の風
窪溜の栖
楽しき独学
居馴れたところ
生きられない
何という不思議な
心やさしの男たち
無縁の夢
濡れた火宅
幼少の砌の
とりいそぎ略歴
命なりけり
肉体の専制
境を越えて
著者等紹介
古井由吉[フルイヨシキチ]
1937・11・19‐2020・2・18。小説家。東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了。大学教員となりブロッホ、ムージル等を翻訳。文学同人誌「白描」に小説を発表。1970年、大学を退職。71年、「杳子」で芥川賞受賞。黒井千次、高井有一、坂上弘らと“内向の世代”と称される。77年、高井らと同人誌「文体」を創刊(80年、12号で終刊)。83年、『槿』で谷崎潤一郎賞、87年、「中山坂」で川端康成文学賞、90年、『仮往生伝試文』で読売文学賞、97年、『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hasegawa noboru
12
荷風、谷崎の両文豪は別として、専門家以外もう誰も手にしないんじゃないかな「ありのまま」を標榜した自然主義の大家たち、徳田秋聲、正宗白鳥、宇野浩二。破滅型の私小説作家、葛西善藏、嘉村磯多。それら明治大正昭和の遠い昔の東京を舞台にした小説を古井由吉とともに読み直すといってもひとつも読んでいないわけだけど、読んだ気にさせてくれるし、古井自身の小説を読んだような気にもなる。書いている今(バブルに浮かれ始めた80年代初期)と比べながら、昔を生きた主人公たちの諸生態をねっとりからみつくように掬い取り抽象化する文体!2021/06/25
qoop
8
江戸という共同体が壊れた後に登場したカオティックな東京人像に迫る意欲作。故郷に馴染まず東京の巷を求めた者、東京生まれで異彩を放ちつつも〈東京人〉といわれれば納得できる者、それぞれの人物像を明治〜大正期の私小説から引き出し、特殊例を積み重ねる中にいきなり著者自身も投入することで、評論が創作活動であり得る顕著な例として成立している。統一感がありつつ変転する読み応えがたまらない。2021/11/20
Gakio
1
随想などと言いつつ、単なる書評ではないかと宇野浩二や葛西善蔵嘉村礒多の師弟の紹介を受けていたら、「とりいそぎ略歴」でそれらの舞台だった東京が突然空襲で爆撃される様が、古井自身の実体験として回想される。家は燃えてなくなり、逃げる市井の人々の「逃げる足は速かった」。 その後は戦後を眺める永井荷風と谷崎に移るが、読む私はかつて東京が爆撃されたという歴史的事実に対する動揺がおさまらない。結局いつも戦後の現代文学作品を読むと、この歴史的事実にぶつかって悄然としてしまう。2024/08/19
十文字
1
大正昭和期の私小説家は東京をどう描いてきたのか。また、著者の古井由吉は東京をどう見てきたのか。最後に荷風と谷崎で締めているのがよかったし、たぶんこの随想の原点はこのふたりなのだろう。2022/01/19
-

- 電子書籍
- 交通工学 土木系 大学講義シリーズ16
-
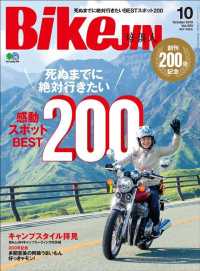
- 電子書籍
- BikeJIN/培倶人 2019年10…



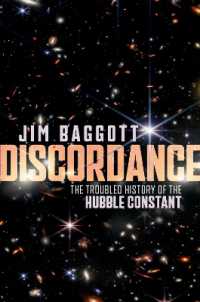
![アニマルアポセカリー [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/49101/4910175741.jpg)


