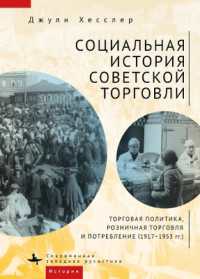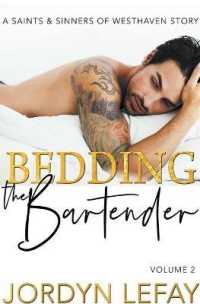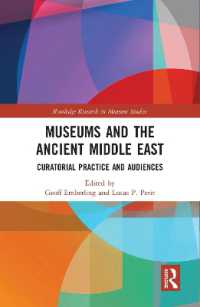出版社内容情報
精神科医が自分を振り返り自らに「発達障害」という診断を下したとき、自分というもののあり方、他者との関係や理解はどのように見えてくるのか。
ASD(自閉症スペクトラム)、ADHD(注意欠陥多動障害)、DCD(発達性協調運動障害)などの診断名で呼ばれる「発達障害」は病気ではないし、必ずしも「障害」ではない。脳のスペックの傾向であり、そのスペックに適した環境に置かれていないがゆえの不適応と考えるほうがはるかに実態に近い。
私のスペックは、たとえば精神科医、牡羊座、A型、DCD、右利き、日本人、大学教授などさまざまに表される。しかし、その中の一つに焦点をあて人としての本質として前景化した形で周りから名指されてしまうと、その「分かられ方」は自分からは切り離され、独自の存在として扱われることになる。
物事を認識すること、人を理解することにおいて、人間の思考の営みは常になにかを捨て去り、排他的に対象を輪郭づけようとするのではないか。ゆで卵が生卵からゆで卵に変貌する臨界点はどこにあるのか。
人工的に作られた名前が必ずしも「定義」から出発しているとはかぎらず、定義もまた定義づけられた瞬間からその「過不足のなさ」は揺らぐことになる。
人を了解すること、人を説明すること、それらの間にはなにか質的な違いがあるのではないか。また自分が自分を分かるということはじつは大きな謎であり、他人のことが分かることの謎へと連続的に連なっている。
本書は、著者による発達障害の自分史を事例としてつつ、「私」あるいは「私」と他者との関係の「分かり方」を考察する。名指すことによって分かるのでなく、繰り返し語らい合い、ともに眼差すことによって「分かる」ことへと接近するだろう道筋を探って。
内容説明
精神科医が自分を振り返り、自らを「発達障害」の一つと診断したとき、自分というもののあり方、他者との関係や理解・了解はどのように見えてくるのだろうか。本来一つにはまとめられない一人間の身体や心の傾向性が、定義づけられた診断名によって一つに名指されることの問題。診断名は説明を可能にするが、それは人を了解することと同じ事態なのか。むしろ何か質的な違いがあるのではないか。互いに「通じる」「分かる」ことへの接近の道を探る。
目次
第1章 発達性協調運動障害者としての「私」史(逆上がりと跳び箱の記憶;「みんな僕のことが好き」という確信 ほか)
第2章 「診断」されるということ(私のスペックと「私」の関係;病名というものには二種類ある ほか)
第3章 了解するということ(三つの異なる「分かってくれない」;静的了解と発生的了解 ほか)
第4章 了解を断念しなければならない時(了解不能という判断;了解を断念してはならない場合 ほか)
第5章 事例「私」の正しい取り扱い方(治療・保護・スプラ;病気として治療する ほか)
著者等紹介
兼本浩祐[カネモトコウスケ]
1957年生まれ。京都大学医学部卒業。現在、愛知医科大学医学部精神科学講座教授。専門は精神病理学、神経心理学、臨床てんかん学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
tamami
かおりん
小鈴
春風
-
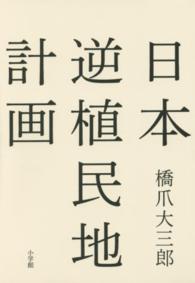
- 和書
- 日本逆植民地計画