出版社内容情報
遊びこそが人間活動の本質、文化の根源である。「遊びの相のもと」に人類の歴史と文化の再構築をこころみた文化史研究、不朽の古典。「人間の文化は遊びにおいて、遊びとして、成立し、発展した」。歴史学、民族学、そして言語学を綜合した独自の研究は、人間活動の本質が遊びであり、文化の根源には遊びがあることを看破、さらに功利的行為が遊戯的行為を圧する近代社会の危うさに警鐘を鳴らす。「遊びの相の下に」人類の歴史の再構築を試みた不朽の古典をオランダ語版全集から完訳。
ヨハン・ホイジンガ[ヨハン ホイジンガ]
著・文・その他
里見 元一郎[サトミ モトイチロウ]
翻訳
内容説明
「人間の文化は遊びにおいて、遊びとして、成立し、発展した」。歴史学、民族学、そして言語学を綜合した独自の研究は、人間活動の本質が遊びであり、文化の根源には遊びがあることを看破、さらに功利的行為が遊戯的行為を圧する近代社会の危うさに警鐘を鳴らす。「遊びの相の下に」人類の歴史の再構築を試みた不朽の古典をオランダ語版全集から完訳。
目次
文化現象としての遊びの性格と意味
言語における遊びの概念の構想とその表現
文化を創造する機能としての遊びと競い合い
遊びと裁判
遊びと戦争
遊びと知識
遊びと詩
形象化の機能
哲学のもつ遊びの形式
芸術のもつ遊びの形式
「遊びの相の下に」立つ文明と時代
現代文化のもつ遊びの要素
著者等紹介
ホイジンガ,ヨハン[ホイジンガ,ヨハン] [Huizinga,Johan]
1872~1945。オランダの歴史学者。ライデン大学教授、同学長を務める
里見元一郎[サトミモトイチロウ]
1929年生まれ。旧制静岡高等学校、東京大学文学部西洋史学科卒業。清泉女子大学名誉教授。専攻は中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
ころこ
かんがく
ちゅん
袖崎いたる
-
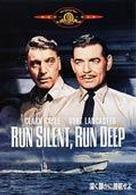
- DVD
- 深く静かに潜航せよ








