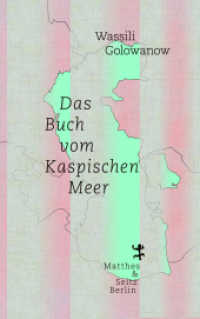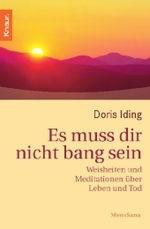出版社内容情報
「遊びをせんとや生まれけむ」――古代文学者が耳を澄ませて読む、中世の「声」と「音」と「ことば」。生のよろこびや悲しみ。遊女や巫女など、歌や舞いを生業として諸国をめぐり歩く女たちが歌い継いだ流行歌「今様」。後白河はそれら、やがて消えゆく「声わざ」を蒐集し、「梁(うつばり)の上の塵も動くほど妙なる歌」という意味の名前をつけた。それが梁塵秘抄である。法皇をも虜にした、アウトサイダーたちの歌うたの調べを、稀代の古代文学者が耳をすませて読む。
第一部 梁塵秘抄の歌
一 我を頼めて来ぬ男
二 遊びをせんとや生まれけむ
三 遊女(あそび)の好むもの
四 楠葉(くすは)の御牧(みまき)の土器作り
五 我が子は十余に成りぬらん
六 我が子は二十(はたち)に成りぬらん
七 舞へ舞へ蝸牛
八 いざれ独楽(こまつぶり)
九 茨小木(うばらこぎ)の下にこそ
十 頭(かうべ)に遊ぶは頭虱(かしらじらみ)
十一 鵜飼はいとをしや
十二 択食(つはり)魚(な)に牡蠣(かき)もがな
十三 吹く風に消息(せうそく)をだに
十四 熊野へ参らむと思へども
十五 仏は常にいませども
十六 拾遺梁塵秘抄歌
第二部 梁塵秘抄覚え書
一 梁塵秘抄における言葉と音楽
二 遊女、傀儡子、後白河院
付
和泉式部と敬愛の祭
神楽の夜――「早歌」について
あとがき
解説=三浦佑之
梁塵秘抄歌首句索引
西郷 信綱[サイゴウ ノブツナ]
著・文・その他
三浦 佑之[ミウラ スケユキ]
解説
内容説明
遊女や巫女など、歌や舞いを生業として諸国をめぐり歩く女たちが歌い継いだ「はやり歌」。後白河院はそれら、やがて消えゆく「声わざ」を蒐集し、「梁の上の塵も動くほど妙なる歌」という意味の名前をつけた。それが梁塵秘抄である。法皇をも虜にしたアウトサイダーたちの歌うたの調べを、稀代の古代文学者が耳をすませて読む。
目次
第1部 梁塵秘抄の歌(我を頼めて来ぬ男;遊びをせんとや生れけむ;遊女の好むもの ほか)
第2部 梁塵秘抄覚え書(梁塵秘抄における言葉と音楽;遊女、傀儡子、後白河院)
付 和泉式部と敬愛の祭(神楽の夜―「早歌」について)
著者等紹介
西郷信綱[サイゴウノブツナ]
1916年、大分県生まれ。東京大学文学部卒。日本の古代文学研究の泰斗。歴史学、人類学、神話学など新たな視野を国文学研究に取り入れ、古典の読みを深化させた。横浜市立大学、ロンドン大学、法政大学などで教鞭をとる。2008年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AN
ホシ
きみー
tayata
月音
-
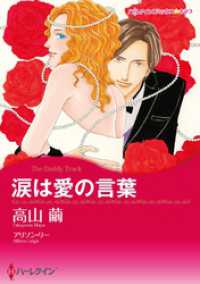
- 電子書籍
- 涙は愛の言葉〈永遠のウエディングベルⅢ…