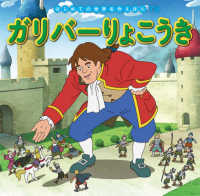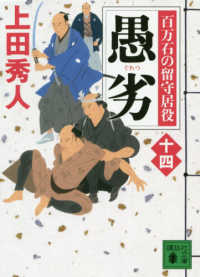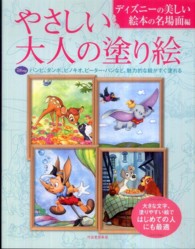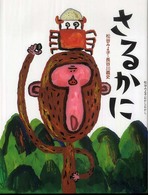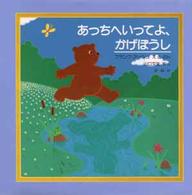出版社内容情報
人間は心をどのように捉えてきたのか。19世紀科学的心理学の誕生に至るまでの思想史的流れを辿り、20世紀心理学の展開を概観する人間は「心」をどのようなものと考え、その作用・構造をどう捉えようとしてきたのか。近代心理学の起源は、1879年ヴィルヘルム・ヴントによる心理学実験室の開設(ライプチヒ大学)の時点とされる。それは「心を対象とする科学」の宣言であった。その後19世紀末から20世紀を通して、心理学はその方法論や認識論に関するさまざまな「革命」を生み出しながら領域を拡大していくことになる。
では、19世紀後半の「始まり」を用意した思想的背景は何だったのか。また古代以来の西洋哲学史のなかで「心の問題」はどのように扱われてきたのか。
本書では、古代ギリシャのプシュケー・プネウマ論から中世霊魂論への変遷を概観し、近代の進化論、生理学研究の進展によって「心理学」が自然科学の一分野として自覚するようになるまでの思想的過程を眺望する。
序 説 近代心理学概観
第1章 ヨーロッパ心理学の起源
(1) ミレトス学派からプラトンまで
(2) アリストテレスの心理学
第2章プシュケーとプネウマ
(1) ヒッポクラテスからカレノスまで
(2) 古代末期の霊魂観:神秘思想の系譜
(3) 中世の霊物学と心理学
第3章 実験心理学の成立
(1) ヘルムホルツと若き日のヴント
(2) 生理学から心理学へ:実験心理学の誕生
(3) ドイツ実験心理学会の形成
(4) 心理学と認識論:初期実験心理学の周辺
第4章 民族心理学の行方
(1) 実験心理学と民族心理学
(2) 民族心理学の歴史的背景
(3) ヴントにおける<行動>概念
(4) 民族心理学の位置づけをめぐる試論
(5) ヴントにおける<心>と<精神>
補論――残された問題
高橋 澪子[タカハシ ミヲコ]
著・文・その他
内容説明
人間は「心」をどのようなものと考え、その作用・構造をどう捉えようとしてきたのか。古代ギリシャのプシュケー・プネウマ論~中世の霊魂論~デカルトの物心二元論を経た後、ヴント心理学実験室の開設=近代心理学の誕生を促した哲学的背景は何だったのか。「心を対象とする科学」の宣言への歴史と、その後の方法論・認識論の革命的変遷を眺望する。
目次
序説―近代心理学史概観
第1部 前近代ヨーロッパにおけるプシュケー論とプネウマ論の変遷(ヨーロッパ心理学の起源;プシュケーとプネウマ)
第2部 一九世紀ドイツの科学思想とヴント心理学の論理(実験心理学の成立;民族心理学の行方)
補説―残された問題
著者等紹介
高橋澪子[タカハシミオコ]
1958年、東京大学教養学部教養学科卒業。1961年、同大学院人文科学研究科心理学専門課程(修士)修了。1969年、同博士課程単位取得退学。1980年より1998年まで専修大学文学部教授を務める。1996年、博士(心理学)の学位を取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
沈黙の魔女。
沈黙の魔女。
ロラン
YASU