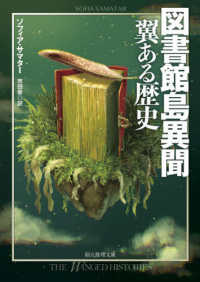出版社内容情報
武家政権を否定した明治国家は、なぜ再び武士を称揚したか。江戸の知的伝統と西洋文明が結合と摩擦を繰り返した近代歴史学の成立事情日本の近代歴史学の成立事情とその背景のドラマを、おもな歴史学上の事件と人物を中心に描き出す。
明治時代とは、江戸期の知的遺産と、急速に流入した西欧の学問が出会った時代だった。歴史学に関していえば、江戸期以来の漢学、特に朱子学の流れと、国学・水戸学の流れ、そこに洋学が結合し、あるいは摩擦を起こしながら、「新しい日本の自画像」を描くべく、「歴史学」が成立し、さらに「国体史観」を形成していったのである。
本書では、鎖国下の平賀源内や林羅山、荻生徂徠らの歴史認識から、明治期の福沢諭吉、森鴎外らの歴史観、実証史学の移植に寄与したドイツの歴史家・リースの働きなどをみながら、「国史」誕生の経過をたどる。
さらに、久米邦武筆禍事件、喜田貞吉と南北朝正閏論争など、「天皇制」との軋轢のなかで近代歴史学が挫折し、あるいは鍛えられていく過程をみていく。
日本の歴史学の成り立ちをあらためて整理し、現代も問われ続けている、「国家」と「歴史研究」との緊張関係という問題を考察する手掛かりとなる好著。
〔原本:『ミカドの国の歴史学』新人物往来社 1994年刊〕
序 出会った歴史──「近代」と「中世」
第一章 「ガリヴァー」の遺産──近代史学のルーツ
1 江戸の中の西洋
2 江戸期の考証学
3 近代史学の界隈へ
第二章 「ミカドの国」の周辺──近代明治の学問事情
1 開化期の史学事情
2 文明史からの解放
第三章 「カイザーの国」の歴史学──西欧史学の移植
1「欧羅巴」史学の履歴書
2 リースと「史学会」
3 リースが見た「日本」
第四章 「ミカドの国」の歴史学──久米事件とその周辺
1 久米邦武筆禍事件
2「ミカドの国」の輪郭
3 久米事件の源流
第五章 「ミカド」から「天皇」へ──喜田事件とその周辺
1 南北朝正閏論争
2 南北朝問題の源流
3「ミカドの国」の終焉
あとがき
関 幸彦[セキ ユキヒコ]
著・文・その他
内容説明
近代日本の歴史学は、江戸期の知的伝統と洋学が結合し、摩擦を起こしながら、「新しい日本の自画像」を描くべく成立した。山片蟠桃や平賀源内の合理的思考。福沢諭吉、西周の学問観。実証史学を移植したドイツの歴史家リースと「国史」誕生への道程。そして久米邦武筆禍事件、南北朝正閏論争など、国家との軋轢の中で歴史学は挫折し、鍛えられていく。
目次
第1章 「ガリヴァー」の遺産―近代史学のルーツ(江戸のなかの西洋;江戸期の考証学;近代史学の周辺)
第2章 「ミカドの国」の周辺―近代明治の学問事情(開化期の史学事情;文明史からの解放)
第3章 「カイザーの国」の歴史学―西欧史学の移植(「欧羅巴」史学の履歴書;リースと「史学会」;リースが見た「日本」)
第4章 「ミカドの国」の歴史学―久米事件とその周辺(久米邦武筆禍事件;「ミカドの国」の輪郭;久米事件の源流)
第5章 「ミカド」から「天皇」へ―喜田事件とその周辺(南北朝正閏論争;南北朝問題の源流;「ミカドの国」の終焉)
著者等紹介
関幸彦[セキユキヒコ]
1952年生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻後期博士課程修了。現在、日本大学文理学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
なつきネコ@たくさんの本に囲まれてご満悦な化け猫
さとうしん
うえ
アメヲトコ