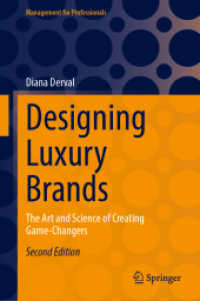出版社内容情報
日本語で書かれたほぼ唯一のパンの文化人類学。膨大な資料と調査に基づいて古今東西のパン食文化を一望。貴重な写真図版を多数収録。豊かに実る穀物を、収穫しては挽いてこねて焼く。
そうして出来た固形物を、本書は「パン」と定義する。
この「パン」作りを、人類は遥か五千年以上前から繰り返してきた。
古来から食べものそのものを意味する特別な存在だったパン。
メソポタミア文明から現代ヨーロッパまでを、膨大な資料と調査に基づいて一望する。
貴重な写真図版も多数収録。
世界各地・諸民族・各家庭で多種多様に継承された、パンの姿と歴史と文化が、この一冊に。
日本語で書かれた、ほぼ唯一の、パンの文化人類学。
はしがき
■序章 米偏世界へ渡来した異邦人
■第一章 パンとは何か
1 パンづくりとは何か
2 ムギ
3 無発酵パンと発酵パン
■第二章 パンの発酵
1 パンはなぜふくらむのか
2 パン種
3 「たねなしパンの祭り」
4 「最後の晩餐」のパン
5 発酵と不浄
■第三章 パン焼き
1 古代遺跡が語るパンの発達
2 古代人のパン焼きのくふう
3 中世のパン焼き
■第四章 パンを焼く村を訪ねて
1 パンを焼く村を訪ねて
2 パンの保存
3 パンと十字印
■第五章 パン文化の伝承
1 パン文化の伝承
2 嫁のパン焼きと姑のパン焼き
3 祭りの象形パン
4 民話の中の記憶
5 パン窯にまつわる暗い影
■第六章 貴族のパンと庶民のパン
1 中世の白パン社会と黒パン社会
2 パン屋
■終章 パンは何を意味してきたか
1 パンのほどこし
2 ある巡礼の古い記録から
注
あとがき
図版リストとクレジット
参考文献紹介
索引
舟田 詠子[フナダ エイコ]
著・文・その他
内容説明
メソポタミアからアルプスまで。ムギ栽培から人工培養イーストまで。古今東西、膨大な調査結果がここに。貴重な図版写真を多数収録。
目次
序章 米偏世界へ渡来した異邦人
第1章 パンとは何か
第2章 パンの発酵
第3章 パン焼き
第4章 パンを焼く村を訪ねて
第5章 パン文化の伝承
第6章 貴族のパンと庶民のパン
終章 パンは何を意味してきたか
著者等紹介
舟田詠子[フナダエイコ]
上智大学独文科卒。78年よりパンの文化史を研究。ウィーン在住、ヨーロッパでフィールドワークをする。千葉大学、東海大学元非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
くらびす
Saiid al-Halawi
しょうゆ
ともくん
-
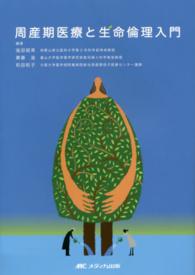
- 和書
- 周産期医療と生命倫理入門