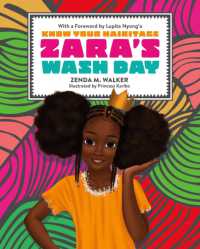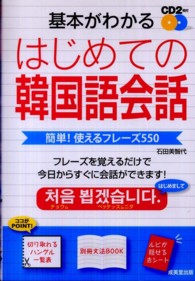内容説明
中国・韓国との「歴史認識のズレ」はここから始まる。戦争とメディアはどのように日本人をつくりあげたか?
目次
はじめに 歴史の断層
第1章 征韓論ふたたび
第2章 戦争はどう伝えられたか
第3章 死んでもラッパを口から離しませんでした
第4章 川上音二郎の日清戦争
第5章 熱狂する人びと、祝捷の空間
第6章 遊戯・学校・軍隊
第7章 死者のゆくえ、日本の位置
むすびに ナショナリズムのねじれ
著者等紹介
佐谷眞木人[サヤマキト]
1962年大阪市生まれ。慶應義塾大学文学部卒。同大学大学院文学研究科博士課程単位取得。博士(文学)。専攻は国文学。現在、恵泉女学園大学人文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
49
国民国家が形作られたイベントとしての日清戦争を、文化的側面から読み解いている。当時の清や朝鮮に対する蔑視は、ストレートな差別のみならず憐れみも絡んでいたようだ。そうした「善意」の視点がより厄介らしい。また、賊軍になった西郷隆盛の意外な人気ぶりや、内村鑑三の賛成論も面白い。反権力であっても今のような反戦とはいかなかった事実がある。旅順虐殺事件を巡る海外と日本国内の報道は、皮肉にも後の南京事件や最近のウクライナ紛争にも類似している。軍歌やオッペケペー節の考察も良い。また、兵士や遺族の戦後、軍神の項目も面白い。2022/06/21
長谷川透
16
イデオロギー操作や無意識化での洗脳は現代でも話題になっている。メディア・政府=強者、視聴者・国民=弱者という図式で以て論が展開され強者が弱者を支配するという結論が出てしまう。近代の戦争もその文脈で語られることが多い。政府が戦争を主導し、戦果による国民の狂乱も敗戦による惨禍も政府の行為の結果による副次的なものだ、という結論である。しかし本書は国民にも戦争を積極的に受け入れる体制が整っていたからこそ政府のキャンペーンは爆発的に浸透したことを指摘している。無意識に弱者に成り下がる大衆こそ、最大の危険因子なのだ。2012/12/01
白義
14
「メディアにおける日清戦争」といった感じの一冊。日清戦争という近代日本が初めて挑む大戦争を発端とし、戦争報道が加熱し、軍人の戦場美談や演劇における国威発揚に合わせた新たなスタイルの登場など、社会史方面から「日本国民」という意識がどう形成されたのかを追っていて、単純な戦史とはちょっと違うアプローチだがなかなか面白い。中でも死んでもラッパを放さなかった水兵の美談が、実は別人だと言われてからどんどん怪しさが発覚しつつも国民には受け入れられちゃうプロセスなどはそれっぽくて笑う。日清戦争に近代日本の深淵を見る一冊だ2019/01/11
めっかち
3
ざっと読み。日清戦争の「歴史的事実」でなく「手触り」を書きたかった、らしい。でも、「手触り」の前に、著者の「日本は悪い戦争をした加害者」というイデオロギーが先に立ってなんだかなぁって感じ。戦争が原則として違法化された令和の今日ロシアを批判するが如く、帝国主義全盛期の明治日本を捉えるって、どうよ。まぁ、色々面白いエピソードも紹介されてて、著者の思想的偏向にさえ目を潰れば、国民国家形成史としてそれなりに面白い。でも、司馬史観を叩いた結果、もっと酷い歴史観に陥ってる気がするんだよなぁ……。2023/02/19
nori
3
I can understand that lunatic nationalism from 薩長 emerged 19th century imperialistic war over Korea and people push government for it. However, is it really the major reason? After Taiwan invasion and Satsuma Rebellion, did rulers want another blood shed?2015/11/17