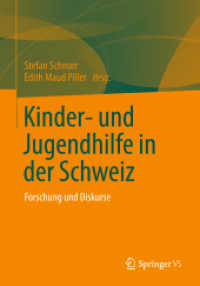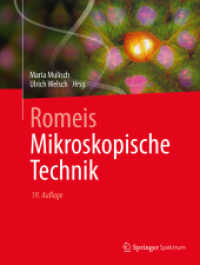内容説明
「若者」「馬鹿者」「よそ者」がいれば町は動く。財政破綻を目前にした離島の小さな町が、名物町長と“日本一安い給料で日本一働く町職員”を中心に、“奇跡の復活”を目指す。「若者」「馬鹿者」「よそ者」とともに、彼らが見つけた“宝物”とは。袋小路・日本の縮図である島の試みの中に、現代日本が直面するさまざまな課題を解決するためのヒントがあった。
目次
其の1 あえて単独での道を選ぶ
其の2 民間の感覚と発想で危機に対する
其の3 意思は言葉ではなく行動で示す
其の4 「守り」と「攻め」の両面作戦
其の5 「島をまるごとブランド化」戦略
其の6 誰もができないと思ったことをやる
其の7 人が変われば島は変わる
其の8 活性化の源は「交流」
其の9 答えは常に現場にある
其の10 ハンディキャップをアドバンテージに
著者等紹介
山内道雄[ヤマウチミチオ]
島根県海士町長(二期目)。1938年海士町生まれ。NTT通信機器営業支店長、(株)海士総支配人を経て、1995年海士町議に当選。二期目に議長就任。2002年町長に初当選。敢えて単独町制を選択し、大胆な行財政改革と地域資源を活用した「守り」と「攻め」の戦略で、島興しに奮戦中である。島根県離島振興協議会会長、全国離島振興協議会副会長、第三セクター「(株)ふるさと海士」社長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュール リブレ
21
著者の講演を聞く機会があり、興味深く拝読しました。限界集落から抜け出すための10の道。一つ一つ、それぞれが言うは易く行うは難し。でも、日本海の離島がどんどん元気になっていくノンフィクションは面白い。2016/11/21
ヤムイチ
5
本当の利益が何か見極める!2018/04/12
nobinobi
3
最後尾から最先端へ。離島である海士町が抱える課題は、将来日本が抱える課題を先取りしている。だからこそ、その課題を解決していくことは、最先端の取り組みへと繋がっていく。数ヶ月海士町にお邪魔したことがあるが、海士町役場の牽引力は物凄いものと肌で感じることができた。2016/10/01
たまちゃん
3
人口減少社会に反して増加を続ける島根県の離島海士町のお話。山内町長の仕掛けが面白い。「松江じゃなく、大阪じゃなく、東京で認められるように」と地産地商をするそのバイタリティは見習うものがある。日本はまだまだ踏ん張りが効きそうだ。2016/01/10
じょに~
3
山内道雄海士町長が考案された海士町での離島振興をご自身で語られたのが本書。島根県の市町村が日本の市町村の10年先を表しているとまで言われているが、その中でも隠岐四島は人口減少や少子高齢化が加速的にすすんで進んでいる。人口増や特産品のブランド化の施策は現状どこの過疎団体でも行っているが、海士町はその中でも施策の独自性だけでなく、財源確保方法が最もユニークだと思われる。人件費削減のために町長の給料を半額にすることについて実際に実行に移せたことが、反響が大きくなったことに繋がったのだろう。2015/09/12
-

- 電子書籍
- 月下の秘め恋 1 ガルドコミックス
-

- 和書
- はじめての材料力学