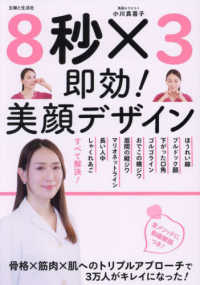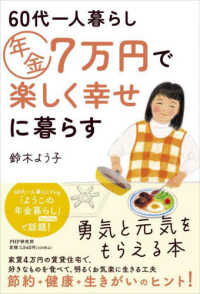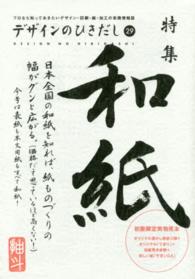目次
第1章 ギョーカイの解体新書(コンテンツとは何か?;特殊なギョーカイ?;コンテンツ支える産業;日本にコンテンツ政策はあるか)
第2章 「流通力の覇権」と「創造力の覇権」(流通力の覇権;創造力の覇権)
第3章 デジタル二重革命(デジタル・インパクト;創造力の氾濫;テレビの憂鬱)
第4章 「次のテレビ」の誕生(パソコンを越えろ;融ける編成表、崩れる視聴率;マイ・チャンネルが切り開く可能性;市場そのものを拡大するには?;「次のテレビ」への課題;純化された新たな流通力)
第5章 映像コンテンツの未来―「テレビの次」へ(クリエイターの覇権の終わり;テレビを越えて;著作権を飛び越える創作のために;求められる新ルール)
著者等紹介
境真良[サカイマサヨシ]
1968年、東京都生まれ。東京大学法学部卒。1993年に通商産業省入省。省庁再編後、経済産業省メディアコンテンツ課課長補佐、東京国際映画祭事務局長などを歴任。2006年4月より早稲田大学大学院国際情報通信研究科客員准教授。専門はコンテンツ産業理論、情報経済論、産業政策論。また、アジア大衆文化、海賊版現象などの研究も行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
26
コンテンツ産業や著作権の話。仕事に関係するかと思って購入。6年前に出版された本で、すでにソースが古くなってしまっているのはこの業界の進化の速さを物語っている。スマートフォンも普及している時代、事業が頭打ちになってしまった場合の活路はどこに見出せるのだろう。うまく棲み分けるか、融合を目指すのか。2014/05/25
春巻き
3
「手軽である」というのは決して軽視できない重要な要因である。なぜなら、それは消費者の消費習慣に直結しているからだ。そしてその消費習慣は日常の中に組み込まれているもので、一度確立すれば容易には消滅しない。かつて、テレビが映画産業を凌駕したときと同じようなことが、今の放送業界において起こっている。2020/12/27
おる太
0
あーこれもっと早い時期に読めばよかったーと後悔した一冊。2016/06/08
v&b
0
今回急いで読んだ。2008年。著者の法律論は凄く広がりがある。「第三章 デジタル二重革命」含め、語り口にも学ぶところ多い。包括的な知識がないと充分に読めないのかもしれない。むろん自分は今回落選だ。が、適度に凹みたい。書き手の(資質の)層も、想定されてる読者のそれも、幾重に分かれてる訳だし。黙っていても年を経ると目減るので、気持は手広くいきたい。2014/12/19
Naota_t
0
この先、テレビはインターネットに爆発的に捲土重来することはないだろう、人口は減り、テレビの売り上げ自体が低迷している世の中で、海外に強みもない業界はこれからどう鎬を削るのか、傍観したい。───クリエイターの目標は技術を進化させ、実用化することではなく、とにかく面白い映像体験を作りだすことにおかれている。結局、テレビはあくまでテレビの延長として進化するのだ、言い換えれば、テレビとパソコンは同じインターネットを基盤としながら、二つの異なるコンテンツの世界を役割分担するように作っていくのだろう。(p.194)2014/07/12