出版社内容情報
日本の「神」とはいったいどのようなものか。日本の「神」を検証し、独自の民俗学をうちたてた折口信夫。古代研究の魅力や歌人として注目されてきたが、はじめてその思想の哲学的意味を跡づける力作。
内容説明
日本の神とは何か?そのこよなく深い思索に分け入る。
目次
序章 折口の情念―「いきどほり」と「さびしさ」
第1章 国学者折口信夫(新しい国学;「神の道徳」と「人の道徳」;折口と平田篤胤;折口の学問的位置;古代の理想―愛欲・猾智;残虐;自由への憧憬)
第2章 『古代研究』における神(常世神;神と精霊;天皇霊;ほかひびと;天つ罪)
第3章 戦後の折口学(神道宗教化に向けて―ムスビの神;既存者;贖罪者としてのスサノヲ;贖罪論の矛盾
著者等紹介
木村純二[キムラジュンジ]
1970年、愛知県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、弘前大学人文学部准教授。専攻は、倫理学、日本倫理思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
5
『一度神の嫁―神の巫女になつて来なければならぬといふ信仰が根本にはあるのです』「折口は、村の神主や長老及び或種の宗教家の持つ「初夜権」が、元来「神聖な行事」であり、「結婚の資格があるかどうかを試す」ものではないと言う。「結婚の資格」云々というのは、具体的には「村の繁殖の為の身体の試験」のことで、そうした「合理的の意味」は、すでに廃れてしまった来訪する神への信仰の「痕跡」なのだと折口は見るのである。折口において、村の繁殖は、あくまで後からの合理的説明なのであって、神への信仰の根本に位置するものではなかった」2016/11/01
-

- 電子書籍
- 貴女依存症 第3話 悪い噂 ラブ・ペイ…
-
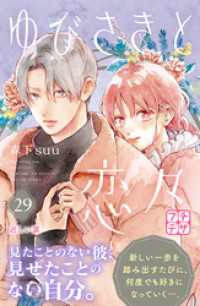
- 電子書籍
- ゆびさきと恋々 プチデザ(29)
-
- 洋書
- Y Cylch
-

- 電子書籍
- 東京カレンダー 2022年 6月号
-
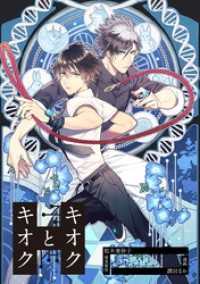
- 電子書籍
- キオクとキオク 第5話 ティアード





