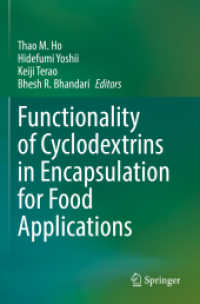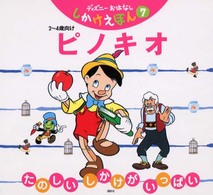出版社内容情報
サンカ、家船、遊行者、遊芸民 漂泊に生きた人びとに出会う。
五木寛之と、賤民文化研究の第一人者による、日本文化の深層を掘り起こす熱き対談。
日本には、士・農・工・商・穢多・非人、という身分制度からはずれて生きるマージナル・マン(周縁の人)がいた。山の漂泊民「サンカ」、海の漂泊民「家船」、「遊行者」、「遊芸民」……。厳しい差別を受けながらも、豊穣たる文化を育んできた彼らの、虚像と実像に迫る。
<著者のことば>
サンカと呼ばれていた人たち、そして遊行者や遊芸民など、いろんな生業をやっている漂泊の民が、この列島の各地を流動して暮らしていた。そして、あたかも体の中を巡っているリンパ球のように、定住民の村や町を回遊していたわけです。そういう人たちによって、この日本列島の文化というものが広められ、またたえず活性化されていたのではないか、というのが、ぼくの年来の幻想なのです。
五木 寛之[イツキ ヒロユキ]
著・文・その他
沖浦 和光[オキウラ カズテル]
著・文・その他
内容説明
五木寛之と、賎民文化研究の第一人者による、日本文化の深層を掘り起こす熱き対談。日本には、士・農・工・商・穢多・非人、という身分制度からはずれて生きるマージナル・マン(周縁の人)がいた。山の漂泊民「サンカ」、海の漂泊民「家船」、「遊行者」、「遊芸民」…。厳しい差別を受けながらも、豊穣たる文化を育んできた彼らの、虚像と実像に迫る。
目次
第1章 漂泊民と日本史の地下伏流(二上・葛城・金剛の山脈と『風の王国』;周縁の人・辺境の人―マージナル・マン ほか)
第2章 「化外の民」「夷人雑類」「屠沽の下類」(柳田國男の問題発掘能力;「化外の民」と「夷人雑類」 ほか)
第3章 遊芸民の世界―聖と賎の二重構造(日本文化とマージナル・マンの系譜;武野紹鴎・千利休―茶道・竹・皮革 ほか)
第4章 海民の文化と水軍の歴史(瀬戸内海のマージナル・ライン;日本民族の源流と海民の系譜 ほか)
第5章 日本文化の深層を掘り起こす(「平地人を戦慄せしめよ…」;「わび」「さび」と底辺の文化 ほか)
著者等紹介
五木寛之[イツキヒロユキ]
1932年福岡県に生まれる。生後まもなく朝鮮に渡り47年にピョンヤンより引き揚げ、のち早稲田大学露文科に学ぶ。その後、PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどをへて66年『さらばモスクワ愚連隊』で第6回小説現代新人賞、67年『蒼ざめた馬を見よ』で第56回直木賞、76年『青春の門 筑豊編』ほかで第10回吉川英治文学賞を受賞。『青春の門』シリーズは総数2000万部を超えるロングセラーとなっている。81年より一時休筆して京都の龍谷大学に学び、のちに文壇に復帰。『日本人のこころ』(全6巻)などにより第50回菊池寛賞を受賞、英文版『TARIKI』はアメリカで2002年のブック・オブ・ザ・イヤー(スピリチュアル部門)に選ばれ、さらに2004年、第38回仏教伝道文化賞を授与された
沖浦和光[オキウラカズテル]
1927年大阪府に生まれる。東京大学文学部卒業。現在は桃山学院大学名誉教授。専攻は比較文化論・社会思想史。これまでに数百にのぼる各地の被差別部落を訪れ、伝承されてきた民俗文化と産業技術を研究。山の民や海の民の歴史にも深い関心を寄せてきた。また、国内外の辺境や都市、島嶼でのフィールドワークを通して、日本文化の深層をさぐる研究・調査を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。