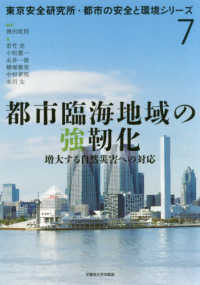出版社内容情報
家族間のトラブルは子供だけでなく夫(妻)も発達障害だったから!? 親子関係の悪化を防ぐ、支援の受け方から対処法までを紹介するひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
家族関係の悪化は、子どもだけでなく親も発達障害だからかもしれません。
「親子ケア」で家族関係が安定すれば親も子も楽になります。
【親子ケアとは】
・発達障害の親と子を中心として家族全員が支援を受けることです。
・親に発達障害の診断がなくても、その傾向があれば有効なケア方法です。
・療育や環境調整など、子どもの支援だけで困難が解消しないときに有効です。
・「家族療法」や「夫婦カウンセリング」で家族の関係性を見直します。
・精神科やカウンセリングセンターで受けられ、主に面談で相談し、助言を受けます。
【トラブル&対応例】
1 父親がADHDの母親と娘に厳しく、叱ってばかりいる
2 母親がASDの父親と息子に合わせすぎて、自己犠牲的に
3 子どもが不登校になり、解決のきざしがみえない
4 家族の会話はあるのに、気持ちが通じ合わない
5 子どもの学習面の困難を、父親がわかろうとしない
6 父親が仕事も家事も完璧で、母親は自信を失っている
7 ADHDの母親がすぐ感情的になって怒る
8 父親が子どものマナーに厳しすぎて険悪に
9 父親はASD傾向で、感謝や謝罪の言葉が足りない
10 祖父母が子どもの教育に口を出しすぎて、つらい
【本書の構成】
第1章 なぜ「親子ケア」が必要なのか
第2章 「家族療法」で関係悪化を防ぐ
第3章 「夫婦カウンセリング」も効果がある
第4章 がんばることに疲れたら、ちょっと休む
《1 なぜ「親子ケア」が必要なのか》
【親子ケアとは】 家族全員が支援を受け、発達障害に対応すること/ 親もケアを受けなければ、子どもがよくならない/ 主な方法は「家族療法」や「夫婦カウンセリング」
【ケース1】 夫と息子が発達障害だとわかり、納得できたAさん
【発達障害とは】 脳機能の障害で、しつけが原因ではない/ ASD、ADHD、LDの三種が重なり合っている
《2 「家族療法」で関係悪化を防ぐ》
【ケース2】 親子ともに診断が出て、家族療法を受けたBさん一家
【家族療法とは】 面談などを通じて、家族の関係性を見直す
【家族でできること】 責め合う関係から、ねぎらい合う関係に変える
【ケース3】 妻と娘の発達障害特性に振り回されていたCさん
【トラブル&対応例】
1 父親がADHDの母親と娘に厳しく、叱ってばかりいる
2 母親がASDの父親と息子に合わせすぎて、自己犠牲的に
3 子どもが不登校になり、解決のきざしがみえない
4 家族の会話はあるのに、気持ちが通じ合わない
5 子どもの学習面の困難を、父親がわかろうとしない
《3 「夫婦カウンセリング」も効果がある》
【ケース4】 妻との関係が悪化し、カウンセリングを受けたDさん
【夫婦カウンセリングとは】
【夫婦でできること】
【ケース5】 発達障害の夫との「家族会議」を習慣化したEさん
【トラブル&対応例】
6 父親が仕事も家事も完璧で、母親は自信を失っている
7 ADHDの母親がすぐ感情的になって怒る
8 父親が子どものマナーに厳しすぎて険悪に
9 父親はASD傾向で、感謝や謝罪の言葉が足りない
10 祖父母が子どもの教育に口を出しすぎて、つらい
《4 がんばることに疲れたら、ちょっと休む》
【ケース6】 ケアをがんばりすぎて、疲れのたまったFさん
【セルフケアとは】 発達障害の人や家族は疲れやすく、休憩が必要/ 自分の疲れやイライラに気づくことが重要
【自分でできること】 ときには親としての自分をオフにする
【ケース7】 夫にも息子にもイライラしにくくなったGさん
宮尾 益知[ミヤオ マストモ]
監修
内容説明
家族関係の悪化は子どもだけでなく親も発達障害だったから!?「親子ケア」で家族関係が安定すれば親も子も楽になる!
目次
1 なぜ「親子ケア」が必要なのか(親子ケアとは―家族全員が支援を受け、発達障害に対応すること;親子ケアとは―親もケアを受けなければ、子どもがよくならない ほか)
2 「家族療法」で関係悪化を防ぐ(家族療法とは―面談などを通じて、家族の関係性を見直す;家族療法とは―家族をひとつの「機能」として考える ほか)
3 「夫婦カウンセリング」も効果がある(夫婦カウンセリングとは―夫婦の間の問題について、面談を受けること;夫婦カウンセリングとは―夫婦仲が安定することで、子どもも落ち着く ほか)
4 がんばることに疲れたら、ちょっと休む(セルフケアとは―発達障害の人や家族は疲れやすく、休憩が必要;セルフケアとは―自分の疲れやイライラに気づくことが重要 ほか)
著者等紹介
宮尾益知[ミヤオマストモ]
東京都生まれ。どんぐり発達クリニック院長。医学博士。徳島大学医学部卒業、東京大学医学部小児科、自治医科大学小児科学教室、ハーバード大学神経科、独立行政法人国立成育医療研究センターこころの診療部発達心理科などをへて、2014年にクリニックを開院。専門は発達行動小児科学、小児精神神経学、神経生理学。発達障害の臨床経験が豊富(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
morinokazedayori
Asakura Arata
たまこ
nizmnizm
みみこ
-

- 和書
- 狸和尚日記