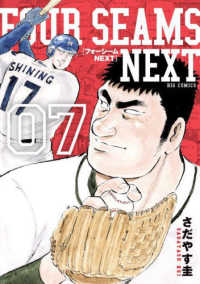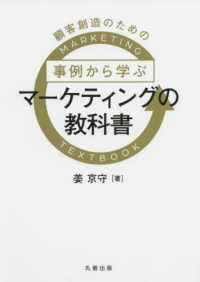出版社内容情報
天皇はなぜ歌を詠み、歌会を開くのか? 万葉集から明仁天皇まで、政治や儀礼と不可分な「和歌」という視点から描く「天皇の歴史」。毎年正月に宮中で開かれる歌会始では、全国から進献される2万首もの歌の中から選ばれた「優秀作」と、皇族たちの作が厳かに披露される。近年では、大震災の被災者や、ペリリュー島の戦いに斃れた人々に思いを寄せた明仁天皇の歌が詠まれた。ではなぜ、天皇は代々、歌を詠み、歌会を開き、歌集を編んできたのだろうか。1500年におよぶ天皇と和歌の「多彩で強固な関係」を通観する。
和歌という表現形式が万葉以来の命脈を保つことができたのは、狭義の文学表現としてのみ存在したのではなく、政治や宗教とも結びつきうる「儀礼」としての性格もあったからだと考えられるという。
誰もが知る百人一首は、天智天皇の歌が巻頭におかれ、『万葉集』は雄略天皇の歌で始まる。雄略天皇の歌には、少女への恋心が謳われるが、そこには武力に長じた征服者の、ライバルたちとの抗争が読み取れるという。平安時代から500年以上にわたって編纂された21もの勅撰和歌集では、多くの歌人が勅撰、すなわち天皇に選ばれることを熱望し、賄賂を用意した。そして鎌倉時代以降は、勅撰集の編纂にも武家が大きく関与し、南北朝時代には、歌道も二つに分裂した。さらに、戦国乱世の秘伝「古今伝受」、江戸時代の宮廷歌壇の活性化、幕末の尊王運動に与えた影響……。
近代に至ると、厖大な数の歌を詠んだ明治天皇は、それが世上に流布されることで「国民国家の元首」としての地位を固め、日米開戦を目前にした昭和天皇は御前会議で祖父の御製を読み上げた――。
これまでの日本社会にとって、天皇とはどんな存在だったのか。「和歌」という視点からそれを検討していく、異色の「天皇の歴史」。
序章 現代の皇室と和歌
1 平成の歌会始
2 歌会始をめぐる人々
第一章 〈愛〉という権力 ――『万葉集』の時代
1 支配者の恋愛と国見
2 恋の演技と君臣の絆
第二章 血筋の権威と勅撰集 ――平安時代
1 漢詩全盛時代の和歌
2 勅撰集の成立
3 藤原氏とのしがらみの中で
4 院政期の和歌
第三章 武力と対決する和歌 ――鎌倉・室町時代
1 後鳥羽天皇の敗北と情熱
2 「両統迭立」の歌風
第四章 文化を体現する天皇 ――江戸時代
1 乱世の古今伝受
2 後水尾天皇の歌壇改革
3 霊元天皇と宮廷歌壇の繁栄
4 尊王運動と和歌
第五章 〈国民国家〉を詠む ――明治時代以降
1 戦争を詠む天皇
2 「歌聖」明治天皇
3 〈大元帥〉から〈象徴天皇〉へ
終章 和歌文学の未来へ
鈴木 健一[スズキ ケンイチ]
著・文・その他
内容説明
被災地やかつての戦地を訪れ、その思いを歌に詠む現代の天皇―。和歌と天皇は、万葉の時代から、多彩かつ強固に結びついてきた。ライバルを次々と倒して即位した雄略天皇は“愛”の歌を詠み、二十一もの勅撰和歌集が五百年以上をかけて編まれ、歌道の秘伝「古今伝受」は、「御所伝受」として江戸時代に存続し、明治天皇は、生涯に十万首におよぶ歌を詠んだ。和歌を通して見えてくる、「日本社会にとっての天皇」とは。
目次
序章 現代の皇室と和歌
第1章 “愛”という権力―『万葉集』の時代
第2章 血筋の権威と勅撰集―平安時代
第3章 武力と対決する和歌―鎌倉・室町時代
第4章 文化を体現する天皇―江戸時代
第5章 “国民国家”を詠む―明治時代以降
終章 和歌文学の未来へ
著者等紹介
鈴木健一[スズキケンイチ]
1960年、東京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。学習院大学文学部教授。専門は、日本近世文学、和歌・漢文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
しゅてふぁん
鯖
さとうしん
たっきー