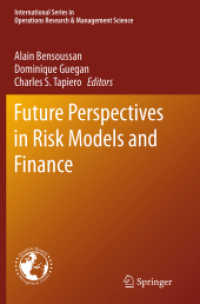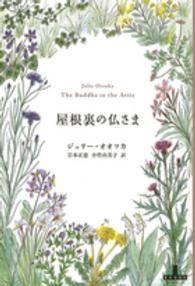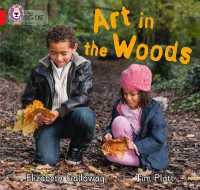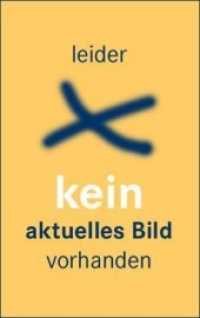出版社内容情報
消えて行った日本語=死語、そのなかでも一段品の落ちる単語=俗語ばかりを収める。明治以降の日本の姿が、強烈に浮かび上がる。消えて行った日本語=死語、そのなかでも一段品の落ちる単語=俗語ばかりを収録。辞典風に五十音順に並べ、さらに詳細な説明や派生を加えた。俗語研究の第一人者による、ひとつの近代日本史。
メッチェン、モダンガール、ニコポン、人三化七、土曜夫人、ヤンエグ、アッシー君……時代に強烈なインパクトを与え、しかし公に使われるわけはないことばたちは、いつの時代も存在した。それらの多くは次第に人々の感覚と合わなくなり、あるいは世相の変化でそれが表す対象を失い、いつの間にか役目を終えて、消えていく。
そんな言葉ばかり約100語をピックアップ。その成り立ちは単語を縮め、くっつけ、ふざけ倒し……実に気が利いている。明治から現代までの時代背景が、どのページからも強く立ち上ってくる。
まえがき
(本編)
あ行
アッシー君/江川る/エンゲルスガール/おかちめんこ ほか
か行
ガチョーン/銀ぶら/ゲバ/ゲル ほか
さ行
サイノロジー/三高/シェー/シャン ほか
た行
ちちんぷいぷい/チョベリバ/チョンガー/テクシー ほか
な行
ナオミズム/濡れ落ち葉 ほか
は行
ハイカラ/フィーバーする/瘋癲 ほか
ま行
みいちゃんはあちゃん/メッチェン ほか
や行
宿六/山の神/ヤンエグ/よろめき ほか
ら行
寮雨/ルンペン/冷コー ほか
(解説)
1 俗語とは
2 流行語の発生と消滅
3 俗語が消えて行く理由
4 若者ことばの変化
米川 明彦[ヨネカワ アキヒコ]
著・文・その他
内容説明
日本人の高い創造性・アレンジ能力は、ことばの創造においても、遺憾なく発揮される。流行りことばは、毒を含み、からかい、笑い飛ばす。一世を風靡しながら、スタンダードになりきれず、賞味期限が切れて退場し、忘れられた「死語」たち。インパクト抜群の小ネタでたどる、近現代日本のもう一つの「風俗史」。
目次
本編(あ行;か行;さ行;た行;な行;は行;ま行;や行;ら行)
解説(俗語とは;流行語の発生と消滅;俗語が消えていく理由;若者語の変化)
著者等紹介
米川明彦[ヨネカワアキヒコ]
1955年生まれ。梅花女子大学教授。学術博士。専攻分野は日本語語彙研究・手話研究。NHK「みんなの手話」で講師を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
くさてる
♡ぷらだ♡お休み中😌🌃💤
袖崎いたる
おさと