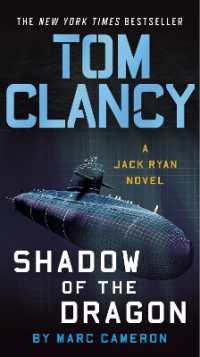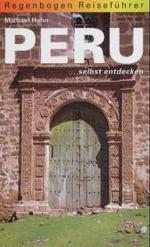内容説明
時は、幕末がいまだ「政治の季節」であった文久期。幕府の権威が根底から揺らぎ、過激志士らの暴発に朝廷がおびえる中、その動向をもっとも注目された男こそ、島津久光であった。久光の指揮の下、小松帯刀、大久保一蔵、中山中左衛門、堀次郎ら、実力ある藩士たちが、京都の中央政局を舞台にして、幕末の行方を決定づける政争をくりひろげてゆく。史料を丹念に読みこみ、幕末政治史にあらたな光をあてる意欲作。
目次
序章
第1章 久光体制の確立と上京政略
第2章 錯綜するイデオロギー
第3章 率兵上京と中央政局
第4章 寺田屋事件の深層
第5章 久光vs.京都所司代―朝廷での政争
第6章 朔平門外の変―薩摩藩最大の危機
第7章 八月十八日政変―首謀者は誰か?
第8章 元治・慶応期の久光・薩摩藩
著者等紹介
町田明広[マチダアキヒロ]
1962年長野県生まれ。上智大学文学部・慶應大学文学部卒業、佛教大学文学研究科修士課程修了。現在、同博士後期課程在籍、明治学院大学職員。専攻は日本近世史(明治維新政治史)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
20
「文久の改革」という大仕事をした割には、西郷・大久保の陰に隠れてしまった印象の久光を高めに評価した本を捜して出会ったもの。斉彬からの信頼が厚く、極めて聡明だったことは、一次資料を駆使して書かれた本書からもうかがえる。特に自分を「地五郞」呼ばわりした西郷を切腹させず使ったのは、確かに久光の胆力もあろう(おそらく山内容堂なら切腹必至と思われる)。また、中川宮との関係も面白かった。ただいくつか気になる点も。まず人物評価の形容詞が大仰で、特に久光は最大限の持ち上げ方。いくら一般評価が低いといっても行きすぎでは。2018/09/20
Emkay
16
1860年代、特に文久年間(1861-64)における、島津久光を中心とした薩摩藩、公武合体、倒幕、王政復古をめぐる出来事が詳述。俯瞰した視点に欠ける、おたく学者本だが、一貫して久光を主人公にした点が出色。島津家が鎌倉時代、薩摩に地頭として送られる以前、京都近衛家に仕えており、その縁が幕末まで続いていたことに驚いた。斉彬死後の京都出兵、倒幕へと傾倒した思想、義理の従兄弟だった小松帯刀の登用、寺田屋事件、藩ぐるみの関与が疑われた朔平門外の変、8月18日の政変の様子は大変詳しい。2018/10/17
Go Extreme
1
久光体制の確立と上京政略: 皇国復古・戦略 錯綜するイデオロギー: 尊王志士と義挙計画 岩倉具視=朝廷の思惑 率兵上京と中央政局: 上京開始と反抗勢力 久光の入京と建白 寺田屋事件の深層: 義挙 伏見義挙計画→事件勃発 長州藩との確執 久光vs.京都所司代: 勅使派遣問題 久光の名代・中川宮 朔平門外の変: 追い詰められる薩摩藩と中川宮 八月十八日政変: 久光召命と上京攻略 政変の主役・高崎正風 政変の首謀者と中川宮 元治・慶応期の久光・薩摩藩: 参予会議と薩長盟約の締結 四侯会議と逢瀬復古への転換2024/09/13
やま
1
決して読み通しやすい本ではないが、面白い。西郷・大久保の影に隠れがちな島津久光の事績を詳細に記述してある。政局での一時的な勝利がかえって後退につながっていくあたりは歴史の皮肉を感じる。2018/08/05
flat
1
島津久光が幕末でどのように動いていたのかが分かる。西郷や大久保の陰に隠れがちであるが彼等が動けたのは久光が薩摩を纏め上げていたからであることは疑いようはない。しかし維新は彼の望んだ姿ではなかったであろうし、そこに彼の居場所も存在していなかった。歴史の皮肉を感じる。2018/08/03
-
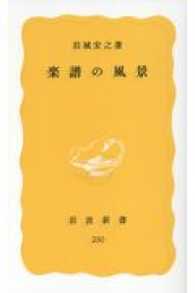
- 和書
- 楽譜の風景 岩波新書