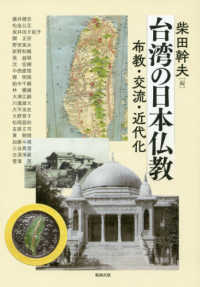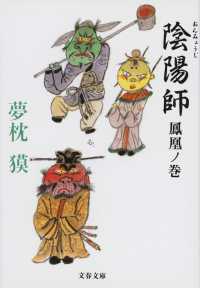内容説明
宗教という営みは何を目標としているのか?キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、そして仏教。異なる世界を出発点としながらも、その上に伝達可能で整合的な知の体系を構築することは、神学的方法論によって可能になる。「聖なるもの」を問う、仏教学第一人者の野心的な講義がはじまる。
目次
第1章 ブッディスト・セオロジー(仏教の神学)
第2章 宗教行為と時間
第3章 「聖なる」空間と時間
第4章 「聖なるもの」と「俗なるもの」
第5章 宗教における現状認識
第6章 宗教と社会
第7章 葬送儀礼における時間
第8章 死者の文化的意味
第9章 龍樹の救済論
第10章 タントリズムの構造
著者等紹介
立川武蔵[タチカワムサシ]
1942年名古屋生まれ。名古屋大学文学部博士課程中退、ハーバード大学大学院にてPh.D取得。国立民族学博物館名誉教授、愛知学院大学文学部教授。専門は仏教学、インド学。著書に『女神たちのインド』(せりか書房、アジア・太平洋賞)ほか多数ある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
sk
6
聖なるもの/俗なるもの、浄なるもの/不浄なるもの、を軸にして、宗教的なものとはどのようなものであるかを豊富な具体例をもとに解説。宗教について考える基本となる本だと思う。2016/10/30
まんぼう
3
「いくつかの操作概念によって宗教現象をどのように説明できるか」。概念の前提、聖なるもの=神聖なもの清浄なものだけではなく死や霊など不気味さや忌みなども含めた、ぞんざいに扱うことを躊躇わせるものすべてのこと。俗なるもの=人の日常のすべて。浄・不浄と必ずしもイコールではない。人間が聖なるもの・俗なるものの区別をしたとき、感じたときに宗教が発生する。聖なるものという感覚は人間に組み込まれた感覚である。無神論者であっても「死体は生ゴミの日に捨ててください」と言われてできる人はまあ少ないと思う。2025/04/27
Tom Ukai
1
ハレとケ、それにケガレを加えてみると、今という時間に生物として生きる自分と、普段は意識していない生物的存在を超越する自分が見えてくるような気がします。仏教から神学的アプローチ。現状認識→目標設定→手段の行為の三要素、行為前、行為中、行為後の時間的段階をベースに、工学的なアプローチも入れ、宗教の構成要素からその定義に迫っていくところは読みごたえバッチリ。これに続くブッティスト・セオロジーのシリーズも読んでみたくなった。2019/02/02
ところてん
1
ブッディスト・セオロジーの第一巻ですが、仏教だけではなく、様々な宗教について述べられています。それぞれ、どのような視点で「聖なるもの」と「俗なるもの」を捉えているのか。比較的身近な考察で、わかりやすくまとめられています。2016/08/12
陽香
0
20060310


![タクテクス光秀戦記明智十兵衛合戦次第 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47986/4798627062.jpg)