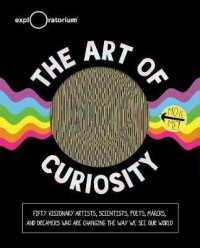内容説明
「声」がブルジョア的記号として、流通しはじめる一九世紀。電気的テクノロジーが、つぎつぎに新たなネットワークを生み出した。大衆の想像力…。資本の欲望…。国家の戦略…。混沌たる草創期のメディア状況と消費社会のダイナミクスを解明する。
目次
序章 声の資本主義
第1章 驚異の電気術
第2章 声を複製する文化
第3章 テレフォンのたのしみ
第4章 村のネットワーキング
第5章 無線の声のネットワーク
第6章 大正のラジオマニアたち
第7章 モダニズムと無線の声
終章 再び、声の資本主義
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
つまみ食い
6
ラジオのような役割(意外にも英米仏などに先駆け19世紀ハンガリーで)を果たしていたり、個人と個人の親密な関係を繋ぐというよりむしろ集団的に使われていた電話やラジオのその草創期の多様な姿に驚く。2024/02/25
takao
1
ふむ2017/11/15
kukikeikou
0
メスメリズム、ここで出てきたか。電話のラジオ的運用、井戸端としての電話ネットワーク、ご近所傍受。電話交換手を勤められない男たち。2017/06/25
富士さん
0
再読。電話とラジオを中心にした電気的に音を伝えるメディアについての歴史と評論の本。イマイチ統一感がなく、テーマがぼやけいているのですが、なんだか魅力を感じました。G,グールドが論ずるレコードみたいに、本書はひとつの答えを提示するのではなく、読者個々が自分のメディア観を養っていくための素材になっています。意図してそういう構成にしていたのなら著者は神ですが、それはないでしょう。私としては、電子メディアの普及の過程がIT技術のそれと軌を一にしているように見えて、新技術の受容に関する型のようなものを感じました。2016/06/30
牧丘一郎
0
最終章の、未来派とラジオとのつながりはなるほどなーって感じです。 しかしそれも、吉見氏の指摘というのではなく、事実とされている見解の紹介という形です。 そこのところにもう少し氏が深入をして、文学作品なんかも参照しながらやって欲しいのですが、どこまでも、メディア論という科目に縛られながら仕事をしているような感じを持ってしまいます。 まった展開というモノが見えないし、参照テキストの紹介のしかたもそっけない。 だから、メディアの問題を取り上げ、それに深入りして考えたいという人にはおすすめできない一冊です。2011/06/26