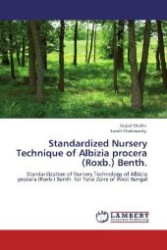- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
派遣切り、二〇〇九年問題、名ばかり管理職、サービス残業…。いま働き方、働かせ方が大きな社会問題になっている。問題の本質は何か。現実的な対応は?基本に立ち返りながら、考えていく。
目次
基本ルールと現場の心得―できないことは約束しない(労働法という名称の法律はない;労働契約の内容は就業規則で決まる;限界のある労働協約、際限のない交渉義務)
職業生活の有為転変―捨てる神あれば拾う神あり(採用にミスマッチはつきもの;辞めるとき、辞めさせるとき;変わるもの、変わらないもの)
裏目に出た規制強化―正義の道は地獄へと通じる(かえって雇用が不安定化した派遣社員;更新に限度が設けられた有期労働契約;待遇改善が難しくなったパート従業員)
口には出せない行政への注文―過ちを改むるに憚ることなかれ(四・六通達と「サービス残業」;告示三七号と派遣・請負の区分;九・二六通達と「二〇〇九年問題」)
ウソのような本当の話―事実(法律)は小説より奇なり(仕事をしない「仮眠時間」も労働時間;組合員は一人でも一〇〇〇人でも権利は平等;労働法の適用を受けない公務員の世界)
著者等紹介
小嶌典明[コジマノリアキ]
1952年大阪市生まれ。神戸大学法学部卒業。国立大学法人大阪大学人事労務室員、同大学院高等司法研究科教授(労働法専攻)。規制改革委員会の参与、総合規制改革会議、規制改革・民間開放推進会議の専門委員として、雇用労働分野の規制改革に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ねぎとろ
0
労働法について歴史的な成り立ちから解説し、現実とのズレや一般的な解釈への批判がなされている。しかし、「常識」を重視する割には、いかにも学者先生といった、ちょっと驚くような発言もちらほら(1927年から1980年の間で、社長と一般職との賃金格差が急速に縮まってきたことから「格差社会とはいえない」いわれても…)。 法律以前に常識あり、という考え方は重要だし、それなりに参考になったが、本書全体の立ち位置がイマイチハッキリしない。エッセイにしては堅すぎる、入門書にしては不親切な作り。2011/09/11