内容説明
草深い東国に浄土真宗の教えを説いた親鸞。その廟堂は覚如によって寺院となった。ささやかな御堂は封建社会の進展にともない拡大を遂げ、真宗は日本史の表舞台にも登場する一大社会勢力となる。本願寺の成立から発展、信長との対戦、時の政権との結びつき、そして東西分立に至る事情など、日本社会の深部に浸透した教団の背景を客観的に考察する。
目次
第1章 真宗の開創(真宗と親鸞の思想;同朋教団)
第2章 本願寺の形成(大谷廟堂;大谷の紛争;本願寺の成立)
第3章 真宗教団の発展(本願寺の整備;真宗諸派の発展;本願寺の北国教線)
第4章 戦国動乱と本願寺(蓮如の生涯;本願寺教団の確率)
第5章 幕藩体制と真宗教団(近世社会の形成;東西本願寺の分立;教団の機構と基盤)
著者等紹介
井上鋭夫[イノウエトシオ]
1923年、石川県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。新潟大学教授、金沢大学教授を歴任。専攻は日本中世史。1974年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
28
ハンパないくらいに煩悩があふれていてヤバい。権力闘争に教団分裂、親鸞死後から江戸時代までの超濃密なヒストリー・オブ・本願寺。唯一の難点といえば、詳細に書きこまれすぎていて流れを掴みにくいところだろうか。とくに印象に残ったのは、親鸞さん亡き後、その墓所(大谷廟堂)の所有管理(=正統)をめぐって、親鸞さん直系の孫世代ですでに政治的なあらそいが起こっていたという話。こういう煩悩まみれの真宗史であっても、親鸞さんは煩悩を否定してるわけでなく「煩悩ありきの浄土往生」なので、ま、セーフなのかな(これまた親鸞システム)2016/05/08
sibasiba
12
親鸞の墓所に建てられた大谷廟堂跡職の争いから始まりから生臭い。聖徳太子信仰が出てくるとは思わなかった。やっぱり蓮如が一番印象に残るな。東西分立にはもう少し詳しく知りたいな。これは1966年増補版が底本だから、最近の本も探してみよう。2013/08/14
moonanddai
8
本願寺がいかにして今の本願寺となったのか…。お隣の(W)宗派でありますが、興味があるところです。弟子を持たないという親鸞の考え方では、教団が生まれることはないはずでしたが、何というかその萌芽は、当時から門徒宗に頼り切った生活費にあったと理解しました。その「体質」は、本願寺になろうとした頃でも変わらず、文字通り年も越せない状況だったとは、(今だから言えるのですが)おかしい。それでも(いわゆる)大谷家を廟堂の留守職にするのには賛否があったらしく、「きちんと勤行します」と墾望状まで出さなければならなかったと…。2023/07/30
1.3manen
8
浄土真宗の親鸞。善光寺と聖徳太子は関係がある(30ページ~)。本願寺の財源は講の拠金による懇志(253ページ)。この懇志ということばは元旦にあっていいことばだと思える。親切心とでもいえるか。住職もまた読経や法話での謝礼で相互依存。講中の寄合場が道場である(254ページ)。福井の穴馬や岐阜白鳥の辺りには惣道場があり、余間で住持の宿泊休憩の場である(255ページ)。世界遺産の五箇山にも道場がある。ムラの中心的存在とは心強い。現代の道場は町内会の寄合所、集会所ということだが、年寄りが多くて心もとない。道場は☆。2013/01/01
nori
5
Acts and persons are just and preciously written. So I could not learn 真宗 from Rev. 法然 and 親鸞 to now as overview of history. I guess that this attitude of study may be criticized by 逆説の日本史. In fact, the book never help to analyze conflict of 東西本願寺 now. 2016/07/08
-
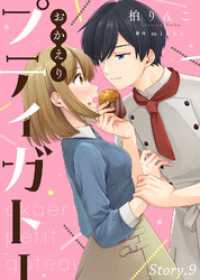
- 電子書籍
- おかえりプティガトー(9) COMIC…







