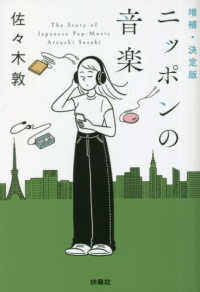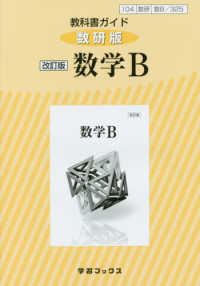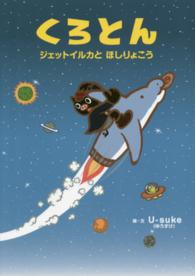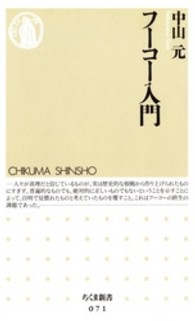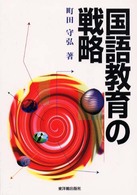内容説明
独特な思想家バタイユ。「消尽」「純粋な贈与」「エロティシズム的欲望」「至高な価値」―彼が提示する概念はすべて彼自身によって深く生きられたことである。パリ国立図書館に勤務、ニーチェ、ヘーゲルなどを学び、非知という考え、共同性の思想へと練られてゆく道筋はどのようなものなのか。表象による認識の限界を越えようとする思考の運動に迫る。
目次
序章 バタイユ的領界―内的経験と異質学
第1章 動物性と人間性
第2章 「俗なるもの」の世界の形成
第3章 聖なるもの、宗教性、エロティシズム
第4章 祝祭=供犠の解明に向けて
第5章 原初的宗教性から制度化された宗教へ
第6章 キリスト教の制度化と否定的神学
第7章 欲望論から文学・芸術論へ
第8章 共同性の問いへ
著者等紹介
湯浅博雄[ユアサヒロオ]
1947年、香川県生まれ。東京大学大学院博士課程、パリ第三大学博士課程修了。東京大学教授。専攻はフランス思想・文学、言語態研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
12
欲望されてるものがなければ禁じる必要はないので禁止の背後には欲望があるというフロイトのテーゼをさらに進めて、破ったらいけない禁止をあえて犯して喜びの度合いが高まる欲望の機制を考えた思想家の解説。本人の記述を詳しく説明するのではなくバタイユ以前以後の様々な文脈を織り交ぜつつ書き上げた、普通の知で捉えきれない領域を捉えようと多弁に語る勢いある文章。初期の著作『ファシズムの心理構造』を起点に置き、聖なる至高者がタブーや宗教的存在から王へと変わり狂気の全体主義集団にまで至ったことに対するバタイユの関心も見通せる。2017/02/26
nappyon
1
わかりやすい。全体の構成がしっかりしていて、内容も重要なところが構成によって強調されていた。参考にしたい。バタイユの様々な著作に渡って横断している思想がうまくまとまっていたので、全体から細部までを理解する助けになった。著作解説やバタイユの生涯についても充実しているので、今後もしばしば参照することになるだろうと思う。2012/06/12
プテラ
0
面白かった!よく知らないバタイユについてよくしれてバタイユを身近に感じられた。2015/09/03
真魚
0
流動的で分かり辛いと噂のバタイユ思想を一冊に凝縮して読み解いてくれる本。バタイユが取り組んだ<聖なる社会学>や文学論などを追うのですが、序章でがっつり体系をさらったあとに各章で細かく見ていってくれるので理解しやすかったです。フロイト理論などを引用して説明する部分も多いので、このあたりの基礎知識があれば更にわかりやすく読めるかも。先に説明した概念を持ち出したい時、省略しないでくり返し説明してくれるのが個人的にはとても助かった。なぜ「神がいなければすべてが許される」のか理解できたので本当に良かったです。2014/12/26
じめる
0
序章で全体の概観した後、各章で思想ごとに整理してくれている。「見たように」や「それは」といった言葉が一区切りの後に頻出し、そこまでの理解を確かめてくれるため、そこが分からなかったら戻って確認する必要がある。バタイユの思想を副題いなる通り<消尽>の思想を根幹に据えてみると、そこには一貫した内なる大きな欲望へと至ろうとする「人間化」された人間の姿が見える。バタイユの思想はフロイトの思想と照応させることで理解が深まるだろうということが言及されているが、その言語観はラカンとの呼応も深いと感じる。2014/03/26